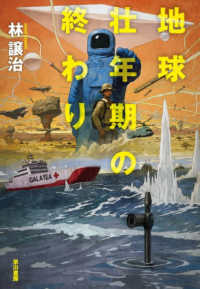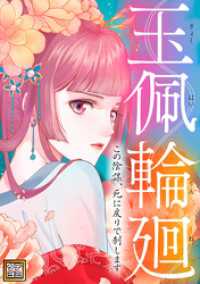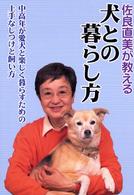出版社内容情報
グローバリゼーションの進む世界経済は、戦争、保護主義の台頭など試練を迎えている。一方で経済的な結びつきは重要性を増々高まっている地域もある。国際貿易論のみならず国際経営学、社会起業論など幅広いジャンルのテーマが織り成す1冊。
内容説明
混迷するグローバル世界を透視する。経済学、経営学、社会起業論にまで及ぶ恩師の教えが接する多彩な研究の姿。
目次
第1部 俯瞰的な視点から―国際貿易論の実証研究から政策論まで―(グローバリゼーションと東アジア;「国際経済学」と「国際経営学」を跨いだキャリアから見えてきたこと;機械産業における国際的生産ネットワークと通商政策;米中貿易紛争が多国籍企業活動に与えた影響;経済制裁の限界―経済学的視点からの再検証;データから見る「脱グローバル化」;日本の自由貿易協定の評価)
第2部 さらなる多様性へ―国際貿易論の応用研究から実践論まで―(経済の複雑性と所得水準;貿易モデルのカリブレーション―モデルとデータのギャップをどう埋めるか;貿易・家計パネルデータの利用課題;グリーン貿易と低炭素経済;ポイントデーと値引きデーのプロモーション効果;これからの「社会の変え方」を探して―ソーシャルイノベーションの二つの系譜とコレクティブ・インパクト)
著者等紹介
小橋文子[オバシアヤコ]
慶應義塾大学経済学部教授。慶應義塾大学で博士(経済学)、ウィスコンシン大学でPh.D.(経済学)取得。学部時代、湘南藤沢キャンパス(SFC)から三田へ経済学を学ぶため足を運び、木村福成研究会(通称「キムケン」)に所属したこと(11期生)が、国際貿易論の研究者としての歩みを始める契機となる。木村先生の温かいご指導のもとで修士・博士課程を修め、恩師が辿られた学問の足跡を追うように渡米。帰国後は白山や青山を経て、再び三田の山へ戻り、現在に至る
木村福成[キムラフクナリ]
慶應義塾大学名誉教授・シニア教授および独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所(IDE‐JETRO)所長。1991年ウィスコンシン大学Ph.D.(経済学)取得。専門は国際貿易論、開発経済学。1982年東京大学法学部卒業後、(財)国際開発センター研究助手として政府開発援助関連の調査研究に従事、その後ウィスコンシン大学にて経済学を学んだ。ニューヨーク州立大学オルバニー校経済学部助教授を経て、1994年より30年間、慶應義塾大学経済学部助教授・教授として三田で研究・教育に携わった。専門は、国際貿易論・開発経済学
清田耕造[キヨタコウゾウ]
慶應義塾大学産業研究所教授。慶應義塾大学で博士(経済学)取得。慶應義塾大学経済学部卒業。木村福成研究会1期生。専門は木村福成先生と同じ国際経済学。学部・大学院(修士・博士課程)を通じて木村先生よりご指導頂きました。日本国際経済学会より2013年に特定領域研究奨励賞(小田賞)、2020年に小島清賞研究奨励賞を、日本経済学会より2017年に石川賞を受賞。著書に『拡大する直接投資と日本企業』(NTT出版、2015年日経経済図書文化賞受賞)ほか
安藤光代[アンドウミツヨ]
慶應義塾大学商学部教授。慶應義塾大学で博士(経済学)取得。国際分野、特に発展途上国に興味があったことから木村福成研究会(4期生)に所属し、恩師の仕事ぶりを見て、実務面も含めて学術面から発展途上国に関わるという選択肢があることを知る。そんな学部ゼミから大学院まで、木村先生の温かくも厳しい指導を受けて、国際貿易論の研究者へと成長し、その後は数多くの共同研究を行う。最近では、本書の他の執筆者との共同研究も多い。国際機関(米州開発銀行や世界銀行研究所)での経験や一橋大学を経て、慶應大学に戻り、現在に至る(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。