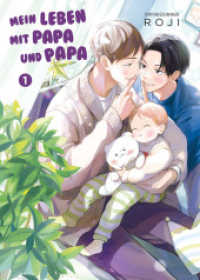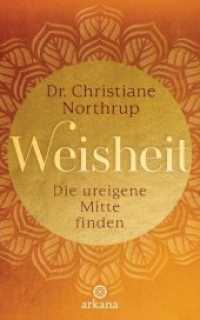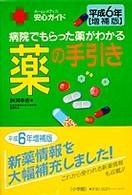出版社内容情報
◆ 日本的雇用システムの原理を聞き取る ◆
働き方の多様化に伴い、労使の関係性についてもさらに進んだ分析が必要とされている。
今世紀に入って大きく変貌したわが国の雇用システムについて、深い聞き取りと質問紙調査によって新たな労使関係のルールと制度を検証し、その上で既存の理論体系の更新、調査方法の改良、分析範囲の拡張を目指す画期的研究。
▼伝統的で地道な分析手法の復権。新たな労使関係のルールと制度を、聞き取りと質問紙調査によって精緻に検証する。
▼日本型雇用システムの実態把握を大きく進展させる意欲的研究。
今日の日本では働き方改革が叫ばれて久しいが、これは主に家族や地域の変化に応じて働き方を変えなければならないという、労働者側の視点から雇用システムを検討した議論といえよう。一方で、企業や労使関係側からの改革案が議論される機会は少ない。雇用する側や労使関係の視点からさらに多くの意見が出され、日本型雇用システムの「現在地」が明らかにされる必要がある。
この「現在地」に最も肉薄する手法が、実地での聞き取り調査と質問紙調査という、一見アナログで地道な手法だ。数字や統計からでは見えてこない真の実態を、理論体系の上にエビデンスとして補強し、より真の姿に近づくことこそが求められている。伝統的だが、ここしばらく途切れている手法を復権させる、働き方の実像に迫る力作。
内容説明
日本的雇用システムの原理を聞き取る。働き方の多様化に伴い、労使の関係性についてもさらに進んだ分析が必要とされている。今世紀に入って大きく変貌したわが国の雇用システムについて、深い聞き取りと質問紙調査によって新たな労使関係のルールと制度を検証し、その上で既存の理論体系の更新、調査方法の改良、分析範囲の拡張を目指す画期的研究。
目次
問題、方法、意味
第1部 競争力の源泉としての技能(職場を構想する力―機械製造工場の事例;「探求」を促す組織と人事―粉体機器の製品開発)
第2部 キャリア・マネジメントの諸相(職能別キャリア管理と長期選抜―同期入社の人事データ分析;非正規化と人材育成の変容―大学職員の事例 ほか)
第3部 労働者の発言のゆくえ(問題探索のための協議―労使協議制の運営;中小企業の中の労使関係 ほか)
第4部 多層的な労使関係(労使関係の中の三者関係―常用型派遣事業の事例;キャリアを支援する労働組合―ワーク・ライフ・バランス施策の導入事例 ほか)
著者等紹介
梅崎修[ウメザキオサム]
1970年生まれ。2000年、大阪大学大学院経済学研究科博士後期課程修了(経済学博士、大阪大学)。専攻:労働経済学、労働史、人的資源管理論。政策研究大学院大学C.O.E.オーラル・政策研究プロジェクト・研究員、法政大学キャリアデザイン学部専任講師、准教授を経て15年より同大同学部教授。2013~14年、The London School of Economics and Political Science訪問研究員。2019~20年、立教大学大学院経済学研究科訪問研究員。2012~20年、中央大学企業研究所・客員研究員、2016年~現在、慶應義塾大学産業研究所・共同研究員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ぽん