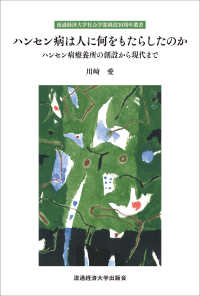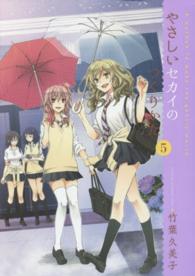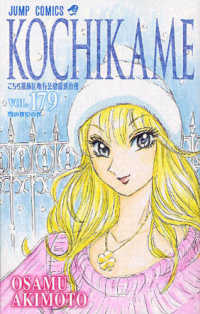出版社内容情報
経済と商業の変遷を背景に、会計制度・会計学の発展過程をたどった、初めての日本会計通史!古来日本国中に於て、
学者は必ず貧乏なり、
金持は必ず無学なり
…故に学者の議論は高くして、口にはよく天下をも治ると云へども、一身の借金をば払うことを知らず。金持の金は沢山にして、或はこれを瓶に納て地に埋ることあれども、天下の経済を学て商売の法を遠大にすることを知らず。蓋し其由縁を尋るに、学者は自から高ぶりて以為らく、商売は士君子の業に非らずと、金持は自から賤しめて以為らく、商売に学問は不要なりとて、知る可きを知らず学ぶ可きを学ばずして、遂に此弊に陥りたるなり。何れも皆商売を軽蔑してこれを学問と思はざりし罪と云ふ可し。
(福澤諭吉(訳)『帳合之法』)
▼天下の事、会計より重きはなし
▼奈良時代の納税管理から江戸期・豪商たちが編み出した日本固有の帳合法を経て、明治期・西洋式複式簿記の受容、そして会計原則と監査制度をめぐる昭和期の挑戦と挫折…。経済と商業の変遷を背景に、会計制度・会計学の発展過程をたどった、初めての日本会計通史!
緒言
謝辞
引用について
<b>序 章 日本の会計の通史</b>
会計史の展開/奈良時代(710?794年)/簿記・会計の定義/歴史の
起点/和式簿記の起源とその源流/西洋からの影響
<b>第1章 江戸時代における和式帳合</b>
江戸時代(1600?1867年)/和式簿記の特徴/和式帳合は複式簿記
か/二重構造と伝播の不在
<b>第2章 明治時代における洋式簿記の導入</b>
明治時代(1868?1912年)/連続と断絶/洋式複式簿記の嚆矢/ブラ
ガ/『帳合之法』/『銀行簿記精法』/政府会計への複式簿記の導入/
近代化の象徴
<b>第3章 明治時代における会計教育と会計学の黎明</b>
明治簿記史の捉え方/洋式簿記の教育/洋式簿記の導入形態/福澤諭吉
と商業教育/下野直太郎の存在意義/固定資産/『会計学』の嚆矢/
大正以降へ
<b>第4章 会計学の発展と財務諸表準則の意義</b>
1920年代から第2次世界大戦まで/会計学発展史の時代区分/上野道
輔とシェアー学説/太田哲三の動態論/ドイツ系の会計制度――商法/
会計制度の展開/財務諸表準則/会計学発展史における財務諸表準則の
意義
<b>第5章 会計プロフェッションの黎明</b>
大坪文次郎,森田熊太郎,東?五郎/立法への曲折/相次ぐ法案提出/
会計学と会計実務/計理士法の制定/いまだ機は熟さず
<b>第6章 昭和時代における会計プロフェッションの逡巡</b>
第2次世界大戦後/計理士と税務/税務代理士法の制定/計理士制度の
改革/「公認会計士」という名称/公認会計士法の成立/制度の輸入と
内実
<b>第7章 近代会計制度の成立</b>
企業会計制度対策調査会と企業会計基準法・会計基準委員会構想/企業
会計原則の設定/企業会計原則,S. H. M.会計原則,黒澤清/企業会計
原則の設定趣意と役割/近代会計制度の成立と会計士監査/監査基準の
設定/法定監査と監査法人/近代会計制度はまだ
文献リスト
索引
著者紹介
友岡 賛[トモオカ ススム]
著・文・その他
目次
序章 日本の会計の通史
第1章 江戸時代における和式帳合
第2章 明治時代における洋式簿記の導入
第3章 明治時代における会計教育と会計学の黎明
第4章 会計学の発展と財務諸表準則の意義
第5章 会計プロフェッションの黎明
第6章 昭和時代における会計プロフェッションの逡巡
第7章 近代会計制度の成立
著者等紹介
友岡賛[トモオカススム]
慶應義塾大学卒業。慶應義塾大学助手等を経て慶應義塾大学教授。博士(慶應義塾大学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 電子書籍
- 転生料理研究家は今日もマイペースに料理…
-

- 電子書籍
- 人生を肴に ほろ酔い百話 だいわ文庫