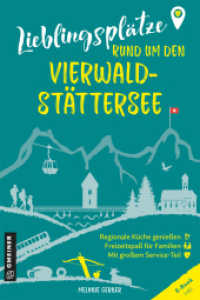- ホーム
- > 和書
- > 教育
- > 教育問題
- > いじめ・非行・不登校・引きこもり
出版社内容情報
本書はスクールカウンセラー、親の会、児童精神科医などが子どもへの対応や支援について解説。親や子どもを支える情報を提供します。
▼本人、親、先生がこの苦悩を乗り越えるために
不登校をどのように理解し、どのようにかかわっていくべきか。
予防と支援の視点から、不登校支援に長年携わっている専門家たちが結集し、大切なポイントを伝えます。
我が子が不登校になったときの親の悩みはとても深いものです。
教師やSCは、予防教育をはじめ、不登校になったときの早期対応・専門機関との連携など、子どもや保護者への具体的支援が必要です。
本書は、教育学・臨床心理学・精神医学の専門家が、不登校の現状を読み解き、不登校をどのように理解し、具体的にどう対応すればよいのかを、今、不登校のことで悩んでいる保護者、学校の先生やSCの方々のために、できるだけわかりやすくまとめたものです。
本書が、我が子への対応や、児童生徒への教育実践を振り返るきっかけとなり、ひいては子どもたちの「生きる力」へとなれば幸いです。
(増田健太郎「はじめに」「おわりに」より)
はじめに ―― 「不登校ゼロ」は、本当によいことなのか(増田健太
郎)
<b>序 章 不登校の現状と取組み</b>(増田健太郎)
不登校児童生徒の実態 / 不登校児童生徒への対応
<b>第1章 不登校の子どものこころと不登校支援</b>
1 不登校という行動の意味 ―― 精神科医の立場から(滝川一廣)
1970~80年代前半の不登校 / 不登校への肯定的視点の登場 /
現在の不登校支援
2 不登校の子どものこころと援助(大場信惠)
どんなときに不登校になるのか /
心理テストの結果から不登校の子どものこころを感じる /
不登校の子どもの気持ち ―― 溺れた人の気持ちから考える /
不登校への援助について
3 不登校児童が示す兆候(サイン)と対応(五十嵐哲也)
最初に見られる兆候(サイン) / 長引いているときの兆候(サイ
ン) / 復帰しかけているときの兆候(サイン) / 重篤な課題を
抱えている不登校の兆候(サイン)
4 保護者への不登校支援と、親の会の役割(加嶋文哉)
「親の会」の発足 / 子ども支援は親の安心から / 二つの形の「親
の会」 / 気持ちの共有 / 陰性感情を言葉にする / 支援を拒否す
る親たちの心情 / 主体は子ども自身
<b>第2章 学校、教師やスクールカウンセラーの対応</b>
1 上手な登校刺激の与え方と留意点(小澤美代子)
不登校の全体像 / 「タイプ分けチェックリスト」 / 「状態像
チェックリスト」 / 「回復を援助する関わり方チェックリスト」 /
不登校の子どもたちへの適切な対応を願って
2 スクールカウンセラーの関わりと心構え(石川悦子)
初期対応 ??登校渋り?? / 不登校の背景 / 相談室登校 /
不登校対応の心構え / 不登校児童生徒数の推移 / スクー
ルカウンセラー等活用事業
3 学級経営と校長・担任の役割:いじめ問題への対応(増田健太郎)
いじめ問題の変遷 / 「いじめ」という言葉で括られる問題 /
事例からいじめ問題の対策を考える / いじめが起こったときの対
応 / 「黄金の三日間」を有効に
<b>第3章 不登校について医学的知見と対応</b>
1 不登校と身体症状の関係(山崎 透)
不登校と身体症状 / 不登校と関連する身体症状の分類 /
不登校の子どもたちの訴える身体症状への対応
2 起立性調節障害が引き金となる不登校(田中英高)
最近、子どもたちの体とこころに起こっていること /
起立性調節障害(OD)とはどんな病気? 不登校とは違うのでしょ
うか? /
起立性調節障害の発症の仕組みは? /
起立性調節障害はどんな方法で診断するのでしょうか? /
起立性調節障害にはこころの問題が関係するのですか? /
起立性調節障害の治療について簡単に教えてください /
担任教師・養護教諭の対応のポイント /
ODの診断治療ガイドラインとはどのようなものですか?
3 発達障害と不登校・ひきこもり(近藤直司・遠藤季哉)
子どもにとっての学校生活 / 自閉スペクトラム症と不登校のメカニ
ズム / 物理的刺激の回避から生じるひきこもり / 特別支援教育の
地域格差と不登校 / ひきこもりリスクの高いケースとは / ひきこ
もりリスクの高いケースへの支援について
4 不登校・発達障害のための薬の基礎知識(黒木俊秀)
なぜ薬物療法を行うのか / 薬物療法には限界がある /
薬物療法のメリットとデメリットをよく知る /
〈参考資料〉基本的な用語、向精神薬の種類と効能、向精神薬の副作
用
おわりに
初出一覧
執筆者紹介
【著者紹介】
増田 健太郎
九州大学大学院人間環境学研究院教授。臨床心理士。教育学博士。専門は臨床心理学、教育経営学。教育と医学の会理事・編集委員。
1959年福岡県生まれ。九州大学大学院人間環境学研究科博士課程単位取得満期退学。小学校教諭、九州共立大学助教授などを経て現職。自由学園アドバイザー、NPO法人九州大学こころとそだちの相談室室長も務める。
著書に『信頼を創造する公立学校の挑戦』(共編著、ぎょうせい、2007年)、『教師・SCのための心理教育素材集』(監修、遠見書房、2015年)など。
内容説明
不登校をどのように理解し、どのようにかかわっていくべきか。予防と支援の視点から、不登校支援に長年携わっている専門家たちが結集し、大切なポイントを伝える。
目次
序章 不登校の現状と取組み
第1章 不登校の子どものこころと不登校支援(不登校という行動の意味―精神科医の立場から;不登校の子どものこころと援助;不登校児童が示す兆候(サイン)と対応
保護者への不登校支援と、親の会の役割)
第2章 学校、教師やスクールカウンセラーの対応(上手な登校刺激の与え方と留意点;スクールカウンセラーの関わりと心構え;学級経営と校長・担任の役割:いじめ問題への対応)
第3章 不登校について医学的知見と対応(不登校と身体症状の関係;起立性調節障害が引き金となる不登校;発達障害と不登校・ひきこもり;不登校・発達障害のための薬の基礎知識)
著者等紹介
増田健太郎[マスダケンタロウ]
九州大学大学院人間環境学研究院教授。臨床心理士。教育学博士。専門は臨床心理学、教育経営学。教育と医学の会理事・編集委員。1959年福岡県生まれ。九州大学大学院人間環境学研究科博士課程単位取得満期退学。小学校教諭、九州共立大学助教授などを経て現職。自由学園アドバイザー、NPO法人九州大学こころとそだちの相談室室長も務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
みぃ
kana