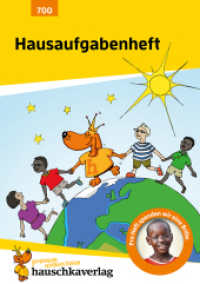出版社内容情報
本書は法の世界に興味を有する入門者への「道しるべ」に、また「法学」と称せられた学科目を学ぶための一助に、という意図の入門書。
「どのような学問分野に取り組む際にも、その第一歩として通過しなければならない関門がある。それは、各分野に特有かつ最小限の共通認識や基礎的事項への理解を掌中にすることであろう。つまり、そこで得た知見を最初の「道具」として、新たな学習への道筋が展開していくことは、「学ぶ」ことに際し、普く共通である。」(「はしがき」から)
本書は、法の世界に興味を有する入門者への「道しるべ」となるために、また多く「法学」と称せられた学科目を学ぶための一助になれば、という意図のもとに編まれた入門書。
法律学を学び、法律を理解するためには、何をすればよいのか。法律世界への実践的アプローチまで踏み込みながら、法律学における共通認識や基礎的事項を理解する。随所に基礎的事項や法制史的なコラムを折り込みながら読者を法の世界へと誘う。日本法制史の研究者の手により書き上げられた特色ある法学入門。
はしがき
<b>第1章 法律学を学ぶために―法律学学習への基礎知識</b>
<b>?T 法律学に関する文献について</b>
<b>1 基本文献</b>
(1) 法律学雑誌
(2) 教科書・概説書
(3) 法律学辞典
(4) 研究書
(5) 判例集
(6) その他
Column 溶け込み方式
<b>2 六 法</b>
(1) 六法という名称の由来
Column 不平等条約
(2) 「六法」(現行法法令集)の利用
Column ポケットサイズの法令集
(3) 六法典の概要
<b>?U 法令に関する基本事項</b>
<b>1 法令の構造</b>
(1) 題 名
(2) 目次・本則・附則
(3) 条 文
(4) 挿入と削除
<b>2 法と言葉</b>
(1) 条文の現代語化
(2) 法の世界と言葉の世界
Column 治罪法の施行にともなう判決文をめぐる取組み
<b>第2章 法律を理解するために―法律学学習に向けての必須知識</b>
<b>?T 法とは</b>
<b>1 当為と存在</b>
<b>2 法と道徳</b>
(1) 法の外面性と道徳の内面性
(2) 強制力の有無
(3) 法は最小限の道徳
Column 刑法と道徳
<b>3 近代法思想史</b>
(1) 近代自然法論
(2) イギリスにおける法実証主義
(3) ドイツにおける法実証主義と自由法学
<b>?U 法源(法の存在形式)</b>
<b>1 法源とは何か</b>
<b>2 日本における成文法</b>
(1) 憲 法
(2) 国の成文法 ―― 法律・命令・規則
(3) 地方公共団体の成文法 ―― 条例・規則
(4) 条 約
(5) 法のピラミッド
<b>3 日本における不文法</b>
(1) 慣習法
ケース?@ 入会集団の慣習と法の下の平等
(2) 判例法
ケース?A 尊属殺重罰規定違憲判決
(3) 条 理
<b>?V 法の種類</b>
<b>1 分類の前提</b>
Column 六法以前
<b>2 公法・私法・社会法</b>
(1) 公法と私法
Column 日本の前近代
(2) 諸学説
(3) 区分の実益
(4) 社会法
(5) 市民法と社会法
<b>3 普通法・特別法</b>
(1) 人を基準とする区分
(2) 事項を基準とする区分
(3) 場所を基準とする区分
<b>4 強行法・任意法</b>
<b>5 実体法・手続法</b>
<b>6 固有法・継受法</b>
Column フランス法直接継受の試み
<b>7 国際法・国内法</b>
<b>?W 法の効力</b>
<b>1 「法の効力」をめぐって</b>
<b>2 法の形式的効力</b>
(1) 時に関する法の効力
Column 法の公布と施行
Column 法の終期と始期
Column 生きている旧刑法
(2) 人に関する法の効力
(3) 場所に関する法の効力
<b>?X 法の解釈と適用</b>
<b>1 法の解釈と適用</b>
(1) 法の解釈
(2) 法の適用
<b>2 有権解釈と学理解釈</b>
(1) 立法解釈
(2) 司法解釈
(3) 行政解釈
<b>3 学理解釈</b>
(1) 文理解釈
(2) 論理解釈
Column 成年後見制度
<b>4 その他</b>
(1) 変更(補正)解釈
(2) 準 用
(3) 擬 制
<b>5 法解釈にあたって</b>
(1) 法解釈のよりどころ
(2) 法的安定性と具体的妥当性
<b>第3章 法律世界への実践的アプローチ</b>
<b>?T わが国の司法制度をめぐって</b>
<b>1 三権(立法権・行政権・司法権)分立とは</b>
(1) 三権分立の意義
(2) わが国における三権分立
<b>2 黎明期のわが国司法制度から</b>
(1) 明治初期における組織の変遷
Column 粟田口止刑事件
(2) 司法省の設置と「司法職務定制」の制定
Column 小野組転籍事件と明治5年司法省第46号達
(3) 大審院の創設
(4) 「治罪法」の制定に伴う制度変更
Column 福島事件と玉乃世履
(5) 裁判所官制
(6) 裁判所構成法
Column 大津(湖南)事件と児島惟謙
<b>?U 現行憲法下における司法権と裁判システム</b>
<b>1 現行憲法下における司法権</b>
(1) 立法権との関係
(2) 行政権との関係
(3) 司法権の独立
Column 特別裁判所をめぐって
<b>2 現行裁判システムについての基本理解</b>
(1) 訴訟の種類
Column 自白と拷問
(2) 三審制
Column 伺・指令裁判体制と内訓条例
(3) 裁判員制度
Column 司法制度改革のゆくえ
(4) 裁判所の種類とその役割
Column 戦後の家族法改正について
(5) 法曹三者 ―― 裁判官・検察官・弁護士
Column 戦前における法曹一元運動と司法資格試験
Column 戦前における検事の位置付け
Column 出入筋と公事師・公事宿
参考文献一覧
事項索引・人名索引
【著者紹介】
霞 信彦
略歴:1951年生まれ。慶應義塾大学法学部教授。慶應義塾大学大学院法学研究科公法学専攻博士課程単位取得退学。法学博士(慶應義塾大学)。
主要著作:『明治初期刑事法の基礎的研究』(慶應義塾大学法学研究会叢書、1990年)、『日本法制史 資料集』(共編、慶應義塾大学出版会、2003 年)、『矩を踰えて 明治法制史断章』(慶應義塾大学出版会、2007年)、峯村光郎(田中実補訂)『改訂・法学(憲法を含む)』(霞信彦ほか改訂、慶應義塾大学通信教育部、2010年)、『法学講義ノート 第5版』(慶應義塾大学出版会、2013年)、『日本法制史?U―中世・近世・近代』(共著、慶應義塾大学通信教育部、2012年)、他。
内容説明
入門者に向けた法の世界の道しるべ。法律学を学ぶためには、何をすればよいのか。初歩から法学を学びながら、法の基礎を理解できる入門書。日本法制史の研究者の手により書き上げられた特色ある法学入門!
目次
第1章 法律学を学ぶために―法律学学習への基礎知識(法律学に関する文献について;法令に関する基本事項)
第2章 法律を理解するために―法律学学習に向けての必須知識(法とは;法源(法の存在形式)
法の種類
法の効力
法の解釈と適用)
第3章 法律世界への実践的アプローチ(わが国の司法制度をめぐって;現行憲法下における司法権と裁判システム)
著者等紹介
霞信彦[カスミノブヒコ]
1951年生まれ。慶應義塾大学法学部教授。慶應義塾大学大学院法学研究科公法学専攻博士課程単位取得退学。法学博士(慶應義塾大学)
原禎嗣[ハラヨシツグ]
1963年生まれ。山梨学院大学法学部教授。慶應義塾大学法学部講師。慶應義塾大学大学院法学研究科公法学専攻博士課程単位取得退学。法学修士(慶應義塾大学)
神野潔[ジンノキヨシ]
1976年生まれ。東京理科大学理学部第一部准教授。慶應義塾大学法学部講師。慶應義塾大学大学院法学研究科公法学専攻後期博士課程単位取得退学。修士(法学)
兒玉圭司[コダマケイジ]
1977年生まれ。国立舞鶴工業高等専門学校人文科学部門准教授。慶應義塾大学通信教育部講師。慶應義塾大学大学院法学研究科公法学専攻後期博士課程単位取得退学。修士(法学)
三田奈穂[ミタナホ]
1983年生まれ。成蹊大学法学部助教。慶應義塾大学看護医療学部講師。慶應義塾大学大学院法学研究科公法学専攻後期博士課程単位取得退学。修士(法学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Yakmy
Ahmad Hideaki Todoroki
-

- 電子書籍
- 魔王様は逆ハーレムが嫌い【タテヨミ】6…
-

- 電子書籍
- 人狼機ウィンヴルガ 8 チャンピオンR…