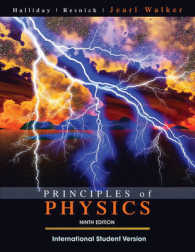出版社内容情報
刑法改正等により新たに導入された刑の一部執行猶予制度を、再犯防止や更生保護の観点から検討し、今後の課題について展望する。
再犯防止・薬物依存治療の切り札となるか?
刑法改正等により新たに導入された刑の一部執行猶予制度を、再犯防止や更生保護の観点から検討し、今後の課題について展望する。
逐条的な解説も付され、研究者はもちろん、実務家必携の書籍!
「一部」執行猶予によって何が変わるのか?
一部執行猶予とはどのような制度なのか?
犯罪者の改善更生と再犯防止という観点からみた場合、刑の一部執行猶予という法制度はどのようにあるべきか。制度と運用の両面から検討し、今後の課題についても展望する。
「改正刑法」「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律」といった、新法の逐条的な解説も付し、研究者はもちろん、実務家必携の書籍!
はしがき
<b>第1編 刑の一部執行猶予の構造と課題</b>
<b>第1章 刑の一部執行猶予制度の法的構造</b>
?T 導入の経緯
?U 意義・目的
1 施設内処遇と社会内処遇の有機的連携
2 満期釈放の解消
3 仮釈放の限界克服
4 薬物依存者の効果的な処遇
5 新たな量刑の選択肢
6 副次的効果としての被収容人員の適正化
?V 法的性格
1 法的性格と法律効果
2 スプリット判決制度との相違
3 一部執行猶予の類型
?W 要件
1 宣告刑
2 前科
3 情状・再犯防止の必要性と相当性
?X 実刑部分と猶予刑
1 算定基準
2 実刑部分と猶予刑の割合
?Y 猶予期間
1 上限と下限
2 算定基準
3 猶予期間と猶予刑の関係
4 起算日
5 猶予期間経過の法的効果
?Z 保護観察
1 裁量的保護観察
2 保護観察の内容と体制
3 特別遵守事項の設定・変更
4 生活環境調整と住居の特定・確保
5 更生緊急保護の適用
?[ 一部執行猶予の取消し
1 必要的取消事由
2 裁量的取消事由
3 取消手続
4 他の刑の執行猶予の取消し
5 仮釈放の取消しとの関係
?\ 一部執行猶予と仮釈放
1 仮釈放の適用
2 法定期間の基準
3 執行率
4 一部執行猶予の取消しと仮釈放の失効
5 取消刑中の仮釈放
6 考試期間主義との関係
?] 量刑
1 一部執行猶予と刑の軽重
2 一部執行猶予の適用類型
3 訴訟当事者から見た一部執行猶予
? 薬物使用者等に対する刑の一部執行猶予
1 目的
2 対象犯罪
3 宣告刑
4 前科
5 情状・再犯防止の必要性と相当性
6 猶予期間と保護観察
(1)必要的保護観察
(2)専門的処遇
(3)指導監督の特則
(4)簡易薬物検出検査
(5)保護観察中の再使用と司法的対応
7 一部執行猶予の取消し
? 遡及適用
<b>第2章 刑の一部執行猶予制度を巡る論議</b>
?T 刑の一部執行猶予制度に対する批判とその検証
?U 制度不要論について
1 副次目的としての過剰収容緩和
2 仮釈放積極化政策の限界
3 仮釈放後の保護観察期間の限界
4 満期釈放の限界
?V 責任主義と残刑期間主義に違背するとの批判について
1 責任主義違反の内容
2 責任主義違反との批判
3 残刑期間主義違反との批判―― 一部執行猶予を巡る第一の誤解
?W 執行猶予制度の趣旨に反するとの批判について
1 ダイバージョンの理念没却
2 一部執行猶予の実質―― 一部執行猶予を巡る第二の誤解
?X 猶予刑を超える猶予期間を設定することへの批判について
1 猶予刑を超える自由制限
2 猶予刑と猶予期間の関係
3 猶予期間から見た二分判決
?Y 厳罰化・刑の長期化に繋がるとの批判について
1 厳罰化の内容
2 刑罰制度の在り方
?Z 量刑判断が困難であるとの批判について
1 量刑における予防的判断
2 個別予防に関する情状立証の程度
3 量刑の面から見た二分判決
?[ 刑の軽重が複雑になり過ぎるとの批判について
1 一部執行猶予と不利益変更禁止の原則
2 執行猶予と不利益変更を巡る判例の立場
3 一部執行猶予と全部執行猶予の関係
4 一部執行猶予と実刑の関係
5 一部執行猶予と一部執行猶予の関係
?\ 受刑者の処遇が困難になるという批判について
1 受刑者の釈放時期と処遇の動機付け
2 矯正処遇の在り方
?] 膠着的な取消しの運用が行われるとの批判について
1 遵守事項違反の程度と取消し
2 遵守事項違反による仮釈放取消しの実情
? 保護観察の体制が不十分であるとの批判について
1 保護観察体制と内容の充実
2 保護観察期間の確保
? 将来の展望
<b>第3章 刑の一部執行猶予と二分判決</b>
――二分判決制度の意義と可能性――
?T 釈放後の再犯と新たな刑罰制度の必要性
1 満期釈放後の再犯と対応の限界
2 仮釈放後の再犯と保護観察期間の限界
3 スプリット判決―― 第三の選択肢
4 新たなスプリット判決―― 二分判決
?U アメリカにおけるスプリット判決の展開
1 ミックス判決・混合刑
2 プロベーションの遵守事項としての拘禁
3 ショック・プロベーション
4 スプリット判決・分割刑
5 二分判決
?V ウィスコンシン州の二分判決制度
1 アメリカにおける量刑改革の経緯と量刑忠実法
2 ウィスコンシン州における量刑改革と二分判決
3 量刑忠実法と二分判決制度の関係
4 二分判決制度の概要
5 拡大保護観察
6 量刑
7 パロールや必要的釈放との関係
8 二分判決の調整・修正制度―― 2001年改正法、2009年改正法、
2011年改正法
9 終身刑の扱い
10 二分判決の実務
?W 我が国における制度の導入可能性と制度設計
1 ウィスコンシン州の二分判決の特徴と我が国への示唆
2 制度の目的
3 必要的仮釈放制度との相違
4 法的性質――刑罰としての複合判決
5 保護観察の法的性質と不良措置―― 刑の一部執行猶予との関係
(1)プロベーション型の保護観察
(2)執行猶予型の保護観察
6 保護観察期間の扱い
7 保護観察の取消しとその効果
8 対象者の範囲
9 仮釈放との関係―― 特に考試期間主義との関係
10 複数刑の執行
?X 将来の展望
<b>第2編 刑の一部執行猶予 関係法令・逐条解説</b>
<b>刑法(明治40年4月24日法律第45号)(抄)</b>
第25条(刑の全部の執行猶予)
第25条の2(刑の全部の執行猶予中の保護観察)
第26条(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)
第26条の2(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)
第26条の3(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行
猶予の取消し)
第27条(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
第27条の2(刑の一部の執行猶予)
第27条の3(刑の一部の執行猶予中の保護観察)
第27条の4(刑の一部の執行猶予の必要的取消し)
第27条の5(刑の一部の執行猶予の裁量的取消し)
第27条の6(刑の一部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行
猶予の取消し)
第27条の7(刑の一部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
第28条(仮釈放)
第29条(仮釈放の取消し等)
刑法等の一部を改正する法律(平成25年6月19日法律第49号)(抄)
附則第1条(施行期日)
附則第2条(経過措置)
<b>薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成25年6月19日法律第50号)</b>
第1条(趣旨)
第2条(定義)
第3条(刑の一部の執行猶予の特則)
第4条(刑の一部の執行猶予中の保護観察の特則)
第5条(刑の一部の執行猶予の必要的取消しの特則等)
附則第1条(施行期日)
附則第2条(経過措置)
<b>刑事訴訟法(昭和23年7月10日法律第131号)(抄)</b>
第333条
第345条
第349条
第349条の2
第350条の14
<b>恩赦法(昭和22年3月28日法律第20号)(抄)</b>
第6条
第7条
第8条
<b>更生保護法(平成19年6月15日法律第88号)(抄)</b>
第1条(目的)
第16条(所掌事務)
第39条(仮釈放及び仮出場を許す処分)
第40条(仮釈放中の保護観察)
第48条(保護観察の対象者)
第49条(保護観察の実施方法)
第50条(一般遵守事項)
第51条(特別遵守事項)
第51条の2(特別遵守事項の特則)
第52条(特別遵守事項の設定及び変更)
第53条(特別遵守事項の取消し)
第54条(一般遵守事項の通知)
第55条(特別遵守事項の通知)
第57条(指導監督の方法)
第58条(補導援護の方法)
第61条(保護観察の実施者)
第62条(応急の救護)
第65条の2(保護観察の実施方法)
第65条の3(指導監督の方法)
第65条の4
第78条の2(住居の特定)
第79条(検察官への申出)
第81条(保護観察の仮解除)
第82条(収容中の者に対する生活環境の調整)
第83条(保護観察付執行猶予の裁判確定前の生活環境の調整)
第85条(更生緊急保護)
第86条(更生緊急保護の開始等)
<b>更生保護事業法(平成7年5月8日法律第86号)(抄)</b>
第2条(定義)
<b>資料編</b>
資料1 法務大臣・諮問第77号
資料2 刑の一部の執行猶予制度に関する参考試案
資料3 法制審議会答申・要綱(骨子)
資料4 法律の提案理由
資料5 国会・法案趣旨説明
資料6 国会・附帯決議
資料7 刑法等の一部を改正する法律・新旧対照条文
初出一覧
索引
【著者紹介】
太田 達也
1964 年生まれ。慶應義塾大学法学部教授。
日本被害者学会理事、日本犯罪社会学会理事、日本更生保護学会理事、最高検察庁刑事政策専門委員会参与、法務省矯正局矯正に関する政策研究会委員、法務省法務総合研究所研究評価検討委員会委員、同犯罪白書研究会委員、一般財団法人日本刑事政策研究会理事、更生保護法人日本更生保護協会評議員、公益財団法人アジア刑政財団理事、公益社団法人被害者支援都民センター理事などを務める。
編著書として、『Victims and Criminal Justice: Asian Perspective(被害者と刑事司法―アジアの展望)』(編著、慶應義塾大学法学研究会、2003)、細井洋子ほか編著『修復的司法の総合的研究』(共著、風間書房、2006)、守山正=安部哲夫編著『ビギナーズ刑事政策(第2 版)』(共著、成文堂、2011)、『高齢犯罪者の特性と犯罪要因に関する調査』(共著、警察庁警察政策研究センター、2013)、『いま死刑制度を考える』(共編著、慶應義塾大学出版会、2014)ほか。
内容説明
刑法改正により導入された、刑の一部執行猶予制度とはどのような制度なのか。再犯防止・薬物依存治療の切り札となるのか。犯罪者を改善更生させ、その再犯を防止するうえで、刑の一部執行猶予という新しい刑の仕組みがどうあるべきかを、制度と運用の両面から分析・検討し、今後の課題について展望する。逐条的な解説も付され、研究者はもちろん、実務家必携の書籍。
目次
第1編 刑の一部執行猶予の構造と課題(刑の一部執行猶予制度の法的構造;刑の一部執行猶予制度を巡る論議;刑の一部執行猶予と二分判決―二分判決制度の意義と可能性―)
第2編 刑の一部執行猶予関係法令・逐条解説(刑法(明治40年4月24日法律第45号)(抄)
薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成25年6月19日法律第50号)
刑事訴訟法(昭和23年7月10日法律第131号)(抄)
恩赦法(昭和22年3月28日法律第20号)(抄) ほか)
資料編
著者等紹介
太田達也[オオタタツヤ]
1964年生まれ。慶應義塾大学法学部教授。日本被害者学会理事、日本犯罪社会学会理事、日本更生保護学会理事、最高検察庁刑事政策専門委員会参与、法務省矯正局矯正に関する政策研究会委員、法務省法務総合研究所研究評価検討委員会委員、同犯罪白書研究会委員、一般財団法人日本刑事政策研究会理事、更生保護法人日本更生保護協会評議員、公益財団法人アジア刑政財団理事、公益社団法人被害者支援都民センター理事などを務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
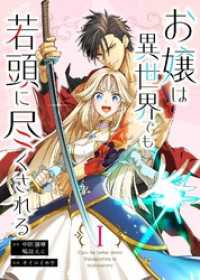
- 電子書籍
- お嬢は異世界でも若頭に尽くされる(1)…