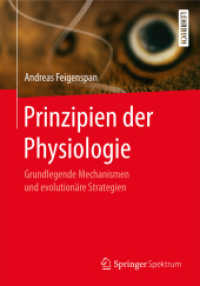内容説明
NHK「大河ドラマ」御所言葉指導の著者によるやんごとなき言葉の歴史とみやびな宮中文化。
目次
第1章 公家言葉集―『公家言葉集存』より(食に関する言葉;衣類に関する言葉 ほか)
第2章 公家言葉はどのようにして生まれたか(公家言葉はなぜ生まれたのか;武家社会に広がる公家言葉 ほか)
第3章 宮中の行事と生活(お火たきの儀式;七草の祝い ほか)
第4章 公家言葉入門―語源から用法まで(食べ物(米・餅、豆・大豆、野菜、魚、調味料、嗜好品、菓子と果物)
鳥 ほか)
著者等紹介
堀井令以知[ホリイレイイチ]
1925年京都市生まれ。言語学者、関西外国語大学教授、新村出記念財団理事長。幼少の頃から言葉に興味を持ち、言語学者を志す。京都大学文学部言語学科卒業ののち、愛知大学教授、南山大学教授を経て、関西外国語大学教授に。言語学とフランス語学の両方で教壇に立つ。御所言葉、京言葉の第一人者として執筆、評論活動を展開する。また「武田信玄」「徳川慶喜」「北条時宗」「利家とまつ 加賀百万石物語」「新撰組!」「風林火山」といったNHK大河ドラマで御所言葉指導を担当し、現在は「篤姫」で指導中(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
あかんべ
4
旧暦の六月十六日のお月見の行事は、復活してほしい行事でした。2014/05/31
reur
2
天皇、皇族、摂家、公卿と上方々は細かく身分の違いが細部に至るまで徹底されていたんだなという事。これは目上も目下も皆尊敬語な昨今の丁寧語とは一線を画すと思う。 年代が下るごとに武家、町方、庶民と下々にまで憧れの言葉という感覚で浸透していき、おかか、おしゃもじなど日常語になっていることばの中にも公家ことば起源の言葉がたくさん残っている一方、戦中戦後にはどんどん使用されるところが無くなり消滅しかかっている言葉でも有るのが悲しいと思う。 「べたべたのかちん」の様に最上級の言葉なのにちょっと印象が違うのも面白い。2013/05/31
Go Extreme
1
公家言葉集―『公家言葉集存』より: 食に関する言葉 衣類に関する言葉 行動、動作 ヒトはモノを掲揚 天王と皇族に対する敬称 公家の敬称 公家言葉はどのようにして生まれたか: 公家言葉はなぜ生まれたのか 武家社会に広がる公家言葉 女性の教養言語として 身分さの世界 文字言葉とは 宮中の行事と生活: お火たきの儀式 七草の祝い お月見 触れ言葉 明治以後の天皇の食生活 公家言葉入門―語源から用法まで: 食べ物(米・餅、豆・大豆、野菜、魚、調味料、嗜好品、菓子と果物) 鳥 衣類 身体に関する言葉 形容の語2022/11/17
mushagumi
0
「お母さん」を「おたあさん」と呼ぶなど、公家言葉の一覧あり。
なっつ
0
団子=いしいしが面白い2012/01/31