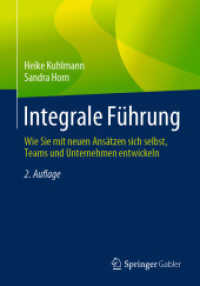- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(日本)
内容説明
かつての日本人の暮らしの姿、食事の形、けじめといった、忘れられないあの風景、あの味を、おばあちゃんたちがさまざまな言葉で語ってくれた。
目次
第1章 北海道と東北(漬物も凍る厳しい冬;養母の生鱈のおすし ほか)
第2章 東京と関東(山育ちが魚屋に嫁いで;江戸川の水で炊いたご飯 ほか)
第3章 中部・東海・近畿・中国(女学校で習ったカレーライス;舅のために毎日かしわを買う ほか)
第4章 九州・沖縄・台湾(丸髷を結ってお弁当を届けてくれた母;座禅豆がたくさん食べられる家にお嫁に行きたい ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
更紗蝦
31
ハウス食品の広報誌『ペパーミル』連載の「聞き書き 暮らしの中の食むかしむかし」というページを再編集したものです。明治以降の家庭の食についての資料の少なさを痛感したことをきっかけに、その時代を生きた人の「生の言葉」を記録するようにした…というコンセプトはとても良いのですが、聞き取りの対象が「嫁・主婦という立場だった人」のみで、お手伝いさんとして台所に立っていた人や、男性であっても台所に立っていた人からの聞き取りがなく、「台所仕事」=「嫁・主婦」というジェンダー観の強化に繋がりかねない構成なのが気になります。2021/02/19
高木正雄
3
いいところのお嬢さんでもあまり良い物を食べていたわけではないようだが、外食は色々いっていたようだ。男と女でご飯が違うとは昭和初期ぐらいまでか。明治生まれの人は恐ろしいほど辛抱強かったのはこういうことも関係あるのだろう。もう少し庶民とか小作人の食事もあれば尚よかった2024/09/22
Humbaba
2
常識というのは意外と最近造られたものも多い。数世代前と現在では様々なものが大きく変わっており、話を聞くだけではまるで現実味を感じられないことすらある。物があふれていて何でも手に入るというのは非常に恵まれたことであり、それによって食べ物も大きく変わってきている。同じものを食べ続けるというのは少し前までは何もおかしくない当然のことであり、同じ味だからと言っていやがるという贅沢は考えられなかった。2025/12/12
海
1
文章が語り口そのままの雰囲気なので、本当におばあちゃんから聞き語りをしているつもりになってほんわかした。多くの方がかまどを「へっつい」、味噌汁を「おみおつけ」と言っていて、確かにこの世代の方ってこう言う言い方してたのを思い出した。インタビューに答えている方々はもうほとんど鬼籍に入られただろうが、こうやって文章は今も昨日語られたかのように鮮やかに残っている。本っていいね。2012/12/01
ショコラテ
1
台所の流しが、最初は座って使うものだったなど、現在では考えられない状況をおばぁちゃん達が語る。惜しむらくは、みんな『ええとこの』お嬢さんだったりするので、一般庶民とは多分違うんだろうな、というところ。御年90overの方が多いので、庶民は栄養状態も悪かったので長生きできなかったのかな…。2012/01/11