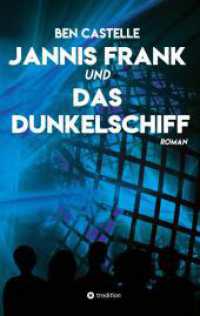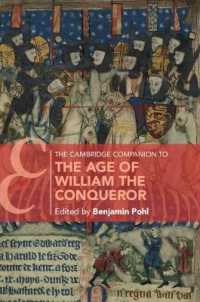内容説明
江戸湾の海防は、パワーポリティクスを基調とした当時の国際関係の中で、幕府の膝元を西欧列強の脅威から防衛するという、徳川幕府にとっての最重要課題の一つだった。文化七年の本格的な台場建設にはじまり、慶応四年に明治維新を迎えるまで、半世紀以上にわたり続いた幕藩体制下の江戸湾海防の変遷を軍事史の観点から検証する。
目次
1 開国前の海防体制(江戸湾の海防計画;会津・白河二藩体制;幕府直轄体制;川越・忍二藩体制;御固四家体制)
2 開国期の海防体制(ペリー来航と湾口防衛の限界;内海への防禦体制構築;品川台場の構造と防禦力;沿岸防衛体制の再編)
3 幕府動乱期の海防体制(江戸湾防備の強化;浦賀奉行所による洋式砲製造;浦賀奉行所による郷兵取立;終末期の江戸湾海防)
著者等紹介
淺川道夫[アサカワミチオ]
博士(学術)、軍事史学会理事・編集委員、日本大学国際関係学部助教。昭和35(1960)年、東京に生まれる。日本大学大学院法学研究科(日本政治史専攻)博士後期課程満期退学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。