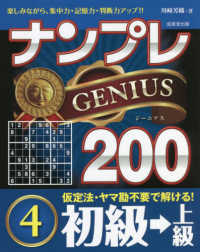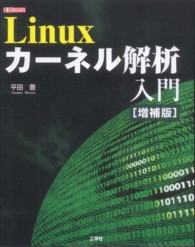出版社内容情報
《内容》 本書の特徴は、化学・生物学を高校であまり学習してこなかった学生にも理解できることを目標に記述しています。また、人間の機能を生理学と生化学に分けて異なった学問として教育するのは理解に苦しむので、あえて初歩の臨床的知識を加えることでより生化学を理解できるように、そして生化学と密接な位置の栄養学の初歩も加えております。 《目次》 第1部 生化学入門 1章 化学への招待状 1.地球の化学組成と生物の化学組成 2.生物体のできるまで 3.無機化合物と有機化合物 4.化学式の表わし方 5.官能基とその化学式 6.その他の化学結合 7.水素イオン濃度 8.緩衝溶液 9.極性分子と無極性分子 10.浸透圧 2章 細胞生物学への入門 1.生き物とはなんだろう 2.「代謝回転」は生きている証拠だろうか 3.典型的な細胞の構造 4.細胞の増殖 5.生体の膜の構造 6.アポトーシス 3章 生理化学への入門 1.生理化学で学ぶ分野 2.脳の生理化学 3.呼吸器の生理化学 4.循環器の生理化学 5.生殖系の生理化学 第2部 ヒトの体の構成成分 4章 人体に含まれる水分 1.水分の人体への出入り 2.体液中の無機塩 3.高齢者の水分量 4.細胞内液と細胞外液 5.血液の緩衝作用と浸透圧 5章 タンパク質の構造と分類 1.タンパク質を構成しているアミノ酸 2.タンパク質の構造と研究 3.体内のタンパク質 6章 酵素の生化学 1.酵素の命名 2.酵素の分類 3.触媒としての酵素 4.酵素のはたらき 5.血液中の酵素のはたらき 6.酵素阻害剤の研究と補充療法 7章 核酸の生化学 1.核酸の研究の歴史 2.核酸の構造 3.核タンパク質の構造 4.RNRの種類 5.RNRポリメラーゼ 8章 タンパク質の合成 1.遺伝の暗号 2.リボソーム 3.タンパク合成の開始 4.転写開始に影響するDNAの因子 5.ペプチド鎖の伸長と終結 6.トランスロケーション 7.抗生物質の作用点 8.翻訳後のプロセッシング 9.組み替えDNAの技術 10.組み替えDNA技術のフローチャート 11.組み替えDNA用語の解説 12.細胞分裂の周期 13.遺伝子治療 9章 アミノ酸の代謝 1.アミノ酸転移と酸化的脱アミノ反応 2.尿素サイクル 3.アンモニアの排出 4.炭素原子1個の移動に必要な化合物 10章 糖質の生化学 1.糖質の種類 2.糖質の消化 3.グルコースの吸収 4.解糖系 5.クエン酸サイクル 6.TCA回路(クレブス回路)の解説 7.呼吸鎖と電子伝達系 8.高エネルギーリン酸結合?○Pの生成 9.グリコーゲンの生成と分解 10.五炭糖リン酸側路 11.糖新生 11章 脂質の生化学 1.脂質の消化吸収 2.脂肪酸 3.脂肪酸の代謝 4.脂質の種類 12章 ステロイドとプロスタグランジン 1.ステロイド 2.プロスタグランジン 第3部 臨床の生化学 13章 ホルモンの生化学 1.内分泌と外分泌 2.ホルモンのはたらき 3.副腎のステロイド・ホルモンのはたらき 4.ペプチド・ホルモンとCyclic AMP 5.その他のホルモン 14章 消化器の生化学 1.口腔での消化 2.胃での消化 3.膵液と腸液による消化 4.消化管から吸収 5.大腸内での発酵 15章 血液の生化学 1.血漿タンパク質 2.血液の凝固のしくみ 3.血液に含まれる物質一覧表 16章 腎臓と尿の生化学 1.糸球体での濾過 2.尿細管での選択的吸収 3.尿細管からの分泌 17章 ヒトに必要な栄養素の生化学 1.人体の所要エネルギーの測定法 2.生活に必要なエネルギーの計算法 3.国別の栄養所要量 4.タンパク質所要量 5.カルシウムの所要量 6.アミノ酸の質の問題 7.生活活動とスポーツのエネルギーの消費量 8.ビタミン所要量 9.ビタミンの化学構造 18章 生化学と関係の深い疾病 1.がんについて 2.糖尿病について
-

- 和書
- わたしにふれてください