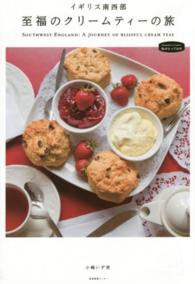内容説明
日本の欧米文化の摂取やキリスト教の宣教に大きな役割を果たした宣教師が、なぜ「招かれざる客」と言われるのか。従来の研究では十分に焦点が当てられなかった日本人と宣教師の関係をさまざまな視点から掘り起こし、近代日本キリスト教受容史の問題点を探る。
目次
最初の宣教師
宣教師と植民地主義
国際主義
アメリカの宣教師
正教会の宣教師
士官学校卒の宣教師
軽井沢と宣教師
女子教育と宣教師
宣教師とその子供たち
日本から神学を学んだ宣教師
女性秘書になった宣教師
戦時中の宣教師
英米の宣教師
日米開戦と宣教師「招かれざる客」としての宣教師
宣教師と中国のキリスト者
内村鑑三と宣教師
追放された宣教師
ドイツの宣教師
クリスマスと宣教師
カトリックの宣教師
三教会からの宣教師
宣教師の悲喜劇
日本の宣教師
異変が起こった宣教師
日本人が宣教師にならない理由
今後の宣教師問題
著者等紹介
古屋安雄[フルヤヤスオ]
1926年、上海に生まれる。1946年、自由学園男子部卒業。1951年、日本神学専門学校(現東京神学大学)卒業。1951‐59年まで、サンフランシスコ、プリンストン神学大学、チュービンゲン大学に留学。プリンストンより神学博士号(Th.D.)。組織神学・宗教学専攻。1959‐97年まで、国際基督教大学教会牧師、同大学宗教部長、教授。その間、プリンストン神学大学、アテネオ・デ・マニラ大学の客員教授、東京神学大学、東京大学、自由学園最高学部の講師を歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
きゃんたか
8
「彼らは一般に善良であって驚くほど名誉心のある人々で……食を節すが、飲むことにかけてはそれほどでもない。……きわめて礼儀正しく、知識欲に燃えた国民である。」(ザビエル)百万人の改宗は彼の人格に負う所大だろう。「日本人はきわめて皮相的で、浮気で、真剣ではない。その意味ではプロテスタントが彼らには合っている。……かれらはいたるところで文明と実利主義と上昇志向の魅力を振りまいている」(ニコライ)三島由紀夫が似たようなことを憂いでいたが。「こんなに自由で、こんなに活躍できる天職が、他にあるでしょうか。」(コルベ)2015/10/21
-

- 電子書籍
- 冷たい心は君限定で溶ける 第32話 拉…
-
![[映像コンテンツ制作のクリエイティブテクノロジー/第1章] - クリエイティブテクノロジーとは](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-0336630.jpg)
- 電子書籍
- [映像コンテンツ制作のクリエイティブテ…