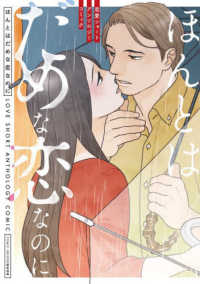内容説明
16世紀、神道・仏教・道教などの影響が混淆した日本宗教と、キリスト教の交差点で、日本人は何を教わり、どのように信じ、実践したのか。従来、外国史料に偏りがちで、宣教師側の視点から語られることの多かったきりしたん研究。その視座を180度転換し、新しい宗教としてキリスト教を受容した「受け手中心」のきりしたん史の再構築を試みる。
目次
第1章 宣教師との出会い―きりしたんの始まり(一五四九~一五八〇年)
第2章 きりしたんの象徴と宣教師のイメージ
第3章 宣教師による適応への努力―きりしたんの発展に向けて(一五八〇~一六一四年)
第4章 きりしたん書を読む
第5章 きりしたんの教えの体系
第6章 日本の宗教文化における「きりしたんの教え」の意義
第7章 きりしたんの儀礼
第8章 棄教・潜伏・殉教―禁制ときりしたん信徒(一六一四年~)
著者等紹介
東馬場郁生[ヒガシババイクオ]
天理大学外国語学部英米学科卒業。シカゴ大学大学院神学部宗教学科、バークレー神学校連合大学院宗教学科修了。Ph.D.(宗教学)。現在は天理大学国際学部外国語学科教授、同大学院宗教文化研究科教授(兼務)、副学長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
夜間飛行
179
初めは領主に強いられて村ぐるみ改宗したため共同体は保たれた。こうした置き換えは宗教的な象徴体系にも起こり、阿弥陀とデウス、数珠とロザリオが共存した。民衆が神学的に正しい信仰より病や死のケアを求めた気持は自然だが、一神教の排他的教義との葛藤も大きかった。日本的信仰は神学校や印刷術の導入後も続き、人員不足の宣教側はゆるしの秘跡を「こんちりさん」(心の中の痛悔)で代用するなど或る程度まで妥協した。結局、宣教師不在のため実行できない儀礼は「おらしょ(祈り)」という形で受け継がれ、日本的な浄化儀礼が前景化してくる。2024/12/08
-
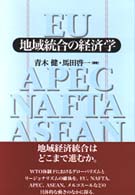
- 和書
- 地域統合の経済学