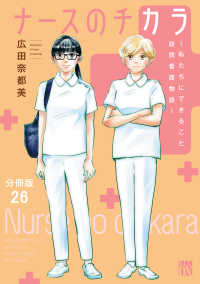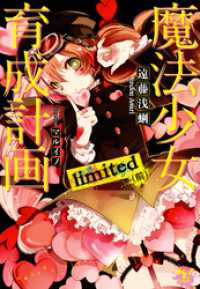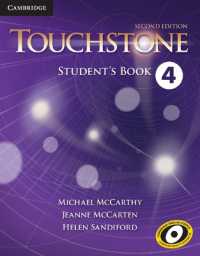- ホーム
- > 和書
- > 社会
- > 社会問題
- > マスコミ・メディア問題
内容説明
新聞販売のビジネスモデルに根深く組み込まれた「押し紙」。部数と広告収入が激減するいま、販売店にすべての矛盾を押しつける構造は、すでに限界に達している―凋落の一途をたどる新聞。長年のタブー「押し紙」を直視しないかぎり、新聞に明日はない―「押し紙」問題は最終局面へ。
目次
第1章 新聞の発行部数が急落している2つの要因
第2章 新聞広告の傾向分析にみる新聞の凋落
第3章 新聞凋落期のメディアコントロール
第4章 「押し紙」問題とは何か?
第5章 「押し紙」の古くて新しい定義
第6章 「押し紙」の歴史と実態
第7章 軽減税率をめぐる議論
第8章 新聞業界が消費税軽減税率にこだわる本当の理由
第9章 新聞凋落の下で進む政界との癒着
著者等紹介
黒薮哲哉[クロヤブテツヤ]
1958年、兵庫県生まれ。フリージャーナリスト。ウェブサイト「MEDIA KOKUSYO」の主宰者。1992年、「説教ゲーム(改題「バイクに乗ったコロンブス」)」でノンフィクション朝日ジャーナル大賞「旅・異文化」テーマ賞を受賞。1998年、「ある新聞奨学生の死」で週刊金曜日ルポルタージュ大賞「報告文学賞」を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Isamash
18
フリージャーナリスト黒薮哲哉2017年著作。新聞発行数の激減とさらにその数字にもまやかしがあることが記されている。そしてその凋落の中で政治権力に生死の鍵を握られつつあることも述べられてる。兵庫県知事選等により今年は、新聞テレビ等オールドメディアの信頼感が大きく毀損された年となってしまった。まともになって欲しいのだが、肝心の当事者たちはSNSの悪口を述べるのみで、自分たちの誤りを正していく気配は無し。まあ押し紙問題でさえ隠微している様では、どうしようも無しか。SNSでのキープレイヤーになれると思うのだが。 2025/01/06
やまやま
6
新聞部数の急落は、インターネットで十分に読める記事が多く提供されていることによる部分も大きい。世界新聞ランキングでは日本は圧倒的に新聞部数の多い国ではあるが、人々の読み方がだいぶ異なるのでは。新聞社主催の講演会などにいくと、参加者平均年齢はかなり高いが、その購読者層もさらに先には減少すると思われる。消費税(率)と新聞社の関係について、財務を良く分析して課題を挙げている。消費税率の上昇によって、押し紙問題は終焉を迎えるのではとも考えられるが、新聞業界のロビイングは引き続き続くとも推測している。 2020/01/29
Taizo
5
2017年の著作。著者はフリージャーナリストで長年新聞業界の闇を取材してきた経歴を持つ。内容は「押し紙」と呼ばれる新聞業界の闇について。新聞業界が発表している「発行部数」は必ずしも「配達している数」と一致せず、およそ3割程度が配られることなく、剰余分は販売店(新聞を配るお店。新聞社とは独立した法人。)積まれ処分されている、らしい。というのも、刷れば刷るほど、広告収入が上がり、新聞社も販売店も儲かっていたから。このようなビジネスモデルは限界があるので、自己変革をしていこうぜというのが著者の主張。2021/10/31
Akio Kudo
3
★★★★ 思った以上に押し紙の問題は大きいのに、メディアで話題にならないことに新聞社の偽善性を、見てしまう2018/12/30
Yukihiro Fujii
2
新聞各社の現実が……大変な状況になっているが、時代の流れに追いついていないのか⁉️ スピード感をはじめ、情報に真実性、情報操作、……など様々な課題が顕在化している。 今まさに、世の中は情報戦争真っ只中でありそんな中でジャーナリストや新聞社の情報の信憑性を読者である我々受け手はどう判断していくかが問われている。 捏造情報には騙されないためには……考えさせられる。2017/07/23