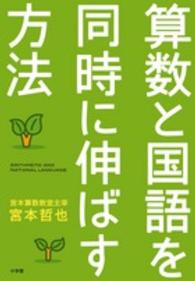内容説明
最後のロックレジェンド、カート・コバーンを境界として、90~ゼロ年代の伝説なき時代にロックはどのように変化し進化を遂げたのか。カウンターカルチャーの重責を免れたオルタナティブロックの歩みを、多彩かつ緻密な考察で検証したロック研究の到達点。
目次
1章 オルタナティブロックの夜明け(グランジの軋み;ジェネレーションX)
2章 波の音楽から渦の音楽へ(ギターサウンドの可能性;白人音楽;合成志向者たち)
3章 表現の美からスポーツの美へ(ロックとスポーツ;体感音響;表現の美、スポーツの美)
4章 日本のオルタナティブロック(Jポップというメインストリーム;日本のオルタナティブロックの始動;日本のオルタナティブロックの展開)
5章 触知的テクノロジー(ロックをめぐる現況;情報社会の音楽)
著者等紹介
南田勝也[ミナミダカツヤ]
1967年、兵庫県尼崎市生まれ。1992年、千葉大学文学部卒業。2002年、関西大学大学院社会学研究科博士課程修了、博士(社会学)。現在、武蔵大学社会学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
阿部義彦
15
YMO世代のおじんにも、楽しめました。歳とると、若い時の音楽だけで、止まってしまって、そもそも音楽を聴かなくなる人多いけど、私は毎日聴いてます、主にnetでは無くて、CD中心と言うのがあれですが。洋楽では90年代以降が花開く時代ですね。ニルヴァーナとマイブラは避けられないですね。日本では97年デビューの、ナンバガ、くるり、スーパーカーをあげてるのは上手いですね。あくまで総論で各論には至っては無いけど、あらましは分かって面白く読めました。でも年寄りから言わせて!なんでムーンライダーズとゆら帝に触れてないの?2022/07/27
権現
8
ニルヴァーナを1つの出発点として、邦洋のロック史・精神史を追いかけながら、消費者との接点変化を中心に、ロックと社会の結びつきを考察した一冊。しかし実際には社会学的な考察というより業界・シーンの変遷とその中で生まれてきたカリスマ達についての議論が多く、「こういう時代だったからこういうバンドが生まれた」以上の内容では無かったかも。インターネット発展以降の話も、他のメディアを語った議論で再三触れられている内容で新しさは無し。メタルが他のロックムーヴメントから孤立したジャンルというのは遺憾ながら返す言葉もない。2017/07/20
y_nagaura
5
「波」と「渦」。旧来のロックとオルタナティブロックの違いがどう違うか、私はレッドツェッペリンとザ・ミュージックの比較で肚に落とした。バンドのプロモーションも、容易になった部分もありつつ、限定的な範囲での成功しか得られなくなっている、との指摘も納得。他にも、好きなミュージシャンの分析がちょこちょこ出てきて興味深い内容だった。2015/03/24
サカモトマコト(きょろちゃん)
4
オルタナティブロックの登場でロック音楽がどのような変化を遂げたのかを解説している本 ニルヴァーナを基点としてニルヴァーナ以降のロックの思想、活動スタイル、リスナーとの関係やレコーディング技術、音響技術の進歩など様々な角度からロックの変化を論じています また、日本のロックの変化を詳しく解説したり、スポーツとの共通点を指摘したりしているところもよかったです。2017/09/10
ちり
4
社会学というタイトルで想像した内容とはちょっと異なり、音圧や機器の発達の話など具体的・技術的な観点からの考察が多い。最近、ジャンルやメディアを問わず、「作家性」を自明視・絶対視しない主張によく出会うな。2017/03/19
-
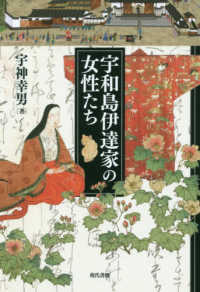
- 和書
- 宇和島伊達家の女性たち