- ホーム
- > 和書
- > 文芸
- > エッセイ
- > エッセイ アンソロジー
内容説明
いかに手紙で伝えるか。染織作家と批評家の魂の交感。
著者等紹介
志村ふくみ[シムラフクミ]
滋賀県生まれ。染織作家・随筆家。重要無形文化財保持者(人間国宝)、文化功労者。2013年、染織の世界を、芸術体験を通して学ぶ場として、アルスシムラ設立。2014年第30回京都賞「思想・芸術部門」受賞。2015年文化勲章受章。著書に『一色一生』(大佛次郎賞)などがある
若松英輔[ワカマツエイスケ]
新潟県生まれ。批評家・随筆家。慶應義塾大学文学部仏文科卒業。「越知保夫とその時代 求道の文学」で第14回三田文學新人賞評論部門当選。『叡知の詩学小林秀雄と井筒俊彦』(慶應義塾大学出版会)で、第2回西脇順三郎学術賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
92
往復書簡とはいうものの、1つの随筆のような感じがします。リルケから始まり志村さんの「晩祷」を読んでのつながりでこの本を読みました。志村さんと若松さんの文学あるいは芸術などの対する真摯な姿勢が伝わってくるような気がします。さまざまな書物などに対してお二人の姿勢というのがこのやり取りによって印象深いものとなっています。さらに志村さんの染色された着物などがカラフルな写真で収められていたり文献一覧などもあり何度も読んでみたい気にさせてくれます。本当にいい本でした。2022/12/06
ちゃちゃ
76
緋の舟に乗って、お二人はどこへ漕ぎ出されるのだろう。染織家であり人間国宝の志村さんと気鋭の批評家である若松さんが真摯に語り合う往復書簡集。洋の東西、時代の古今、互いのフィールドを超え美の秘義に迫ろうとするお二人の書簡は、互いへの敬愛に満ち思念の深みを映し出して魂の交流を思わせる。若松さんは志村さんの作品に「芸術とは、畢竟、光の業」だと教えられたという。美に光を見いだし、その実現を祈る者が真の芸術家であると。私はただただ深い感銘を受け、お二人の作品が私にとって祈りに満ちた光であり希望であることに感謝したい。2017/12/31
Mijas
58
全てが上質な一冊。2014年5月から約一年半の志村さんと若松さんの往復書簡だが、文章がとても美しい。時候の挨拶ひとつ取り出してみても、季節の移ろいが色彩を帯び、絵画を観ているかのよう。「散りしいた花びらが…最後の桜からの伝言…」という結び方に嘆息し、手紙文ならではの相手を気遣う言葉に心地良さを感じる。伝えること、表現することを使命とする二人が「今しか書くことができないもの」を言葉として紡いでいく。「美を創り出すものは心。」感じたままの言葉は美しく尊い。「鍵」となる言葉のリストが、読書の意味を教えてくれる。2017/03/25
ぶんこ
52
志村ふくみさんの落ち着いた大人の着物が好きな一ファンにすぎない私が、この本を読んで一ファンなどとはおこがましいと畏れおののきました。本業だけでもご多忙でしょう。その日々の中のどこにここまで深く物事を考察する時間があるのでしょうか。ただただ畏れいりました。若い頃にリルケに傾倒しましたが、志村ふくみさんや若松さんのような深みにまで入り込むことがなかったです。自分と比べるように恥ずかしいと言うのもおこがましい。雲の上からのお二人の書簡集。志村さんへの尊敬の念が天井知らずとなりました。2019/03/11
やいっち
48
本書を読み始めた日、以下のように呟いた: 染色作家の志村ふくみ氏と批評家の若松英輔氏との往復書簡。共に我輩には初めての人物。染色作家という仕事に惹かれた。もっと云うと、石工にしろ、大工にしろ、彫刻家(わけても石碑や墓石の)にしろ、漆喰などの左官、電気(電機)工事士、歯科技工士、彫金作家などなど、実務の専門家の仕事や発想、心構えが気になる。人間国宝の志村氏を彼らと同列にするわけではないが、日頃、接することのない、プロの仕事(に対する姿勢)を垣間見たいのだ。2019/04/11
-

- 電子書籍
- 王妃様は離婚したい 分冊版(20) ~…
-
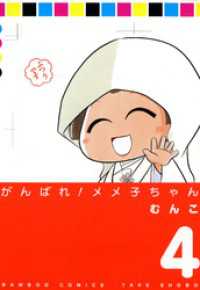
- 電子書籍
- がんばれメメ子ちゃん (4) バンブー…






