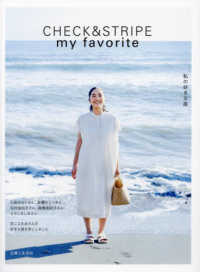出版社内容情報
人の学びを探究し,学習環境をデザインする学習科学。生成AIの教育利用など学びのあり方が根本から問い直される中,学習科学の知見を現場の教育実践にどう活かせるか。「主体的・対話的で深い学び」を学習科学の理論で読み解き,授業づくりや授業研究に実現する道筋をガイド。教員研修のテキストとしても活用できる。
【目次】
刊行に寄せて
本書のトリセツ
第1部 学習科学への招待
第1章 「学び」を探究するワケ
1.1 なぜ“How People Learn”か?
1.2 人はどのように「学ぶ」のか
1.3 何が「学び」を生み出すのか
第2章 「学び」が意味するコト
2.1 獲得メタファの学び
2.2 参加メタファの学び
2.3 「学び」の理解はどのように変わってきたか
第3章 今求められる「学び」
3.1 知識創造メタファの学び
3.2 知識構築の学び
3.3 知識構築を実践する
第2部 学習指導要領への学習科学的アプローチ
第4章 深い学び:資質・能力の3つの柱を「バランスよく育てる」とは
4.1 熟達化
4.2 生産的失敗
4.3 メタ認知
第5章 対話的な学び:何のための対話・協働か
5.1 建設的相互作用
5.2 学習共同体
5.3 CSCL
Column リフレクティブディスコース(省察的談話)
第6章 主体的な学び:主体的であるとはどういうことか
6.1 自己調整学習
6.2 社会共有的調整学習
6.3 shared epistemic agency
Column 実行機能
第7章 何のための探究か
7.1 探究学習で理解が深まるとは
7.2 探究学習をどのように設計するのか
7.3 探究に協働は必要か
Column 総合的な学習の時間における「探究の過程」を再考する
第3部 学習科学で生み出すこれからの学び
第8章 「学び」を探究する方法論
8.1 学習科学の独自の研究方法:DBR
8.2 学習科学の独自の研究方法:DBIR
8.3 学習科学を参照した授業研究の改善事例
第9章 「学びの探究」入門
9.1 探究の心得:先行研究を読む
9.2 探究を形づくる:計画・実践・まとめのポイント
付録:本書を使った学び方
引用文献
索引
目次
第1部 学習科学への招待(「学び」を探究するワケ;「学び」が意味するコト;今求められる「学び」)
第2部 学習指導要領への学習科学的アプローチ(深い学び:資質・能力の3つの柱を「バランスよく育てる」とは;対話的な学び:何のための対話・協働か;主体的な学び:主体的であるとはどういうことか;何のための探究か)
第3部 学習科学で生み出すこれからの学び(「学び」を探究する方法論;「学びの探究」入門)
著者等紹介
河野麻沙美[カワノマサミ]
上越教育大学大学院学校教育研究科・准教授。静岡大学大学院教育学研究科附属学習科学研究教育センター(RECLS)・学外協力研究員。博士(教育学)。東京大学大学院教育学研究科後期課程単位取得退学、日本学術振興会特別研究員(DC2、PD)、東京大学大学院教育学研究科附属学校教育高度化センター助教、東京大学海洋教育促進研究センター特任講師、上越教育大学大学院学校教育研究科講師を経て、現職
河〓美保[カワサキミホ]
静岡大学教育学部・准教授。静岡大学大学院教育学研究科附属学習科学研究教育センター(RECLS)・センター長。博士(教育学)。京都大学大学院教育学研究科博士後期課程学修認定退学。京都大学高等教育研究開発センター助教、追手門学院大学心理学部講師、准教授を経て、静岡大学に着任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。