出版社内容情報
「パン【も】買った/返事【も】しない」「勉強した【が】不合格だった/野球もする【が】水泳もする」。聴覚障害教育現場では日本語指導の難しさ,中でも特に助詞の使い分けの指導の難しさが在る。生活言語から学習言語への移行をめざし,本書では副助詞や接続助詞を中心に(接続詞も加え),それらの手話表現を考える。
はしがき
推薦のことば
聴覚障害児教育に携わる方々へ
編集にあたっての「方針」
9章 「並列」や「添加」に関わって
10章 「比較」や「程度」に関わって
11章 「限定」や「強調」に関わって
12章 「順接」や「継起」に関わって
13章 「逆接」に関わって
14章 「言い換え」や「転換」に関わって
副助詞,接続助詞,接続詞が適切に使えるかな?
引用・参考文献
手話イラスト名検索
あとがき
【著者紹介】
脇中 起余子
京都府立聾学校教諭
目次
9章 「並立」や「添加」に関わって
10章 「比較」や「程度」に関わって
11章 「限定」や「強調」に関わって
12章 「順接」や「継起」に関わって
13章 「逆接」に関わって
14章 「言い換え」や「転換」に関わって
著者等紹介
脇中起余子[ワキナカキヨコ]
新生児の時に、薬の副作用で失聴。京都大学大学院教育学研究科博士後期課程中退。龍谷大学大学院文学研究科博士後期課程修了。現在、京都府立聾学校教諭(教育学博士・学校心理士)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
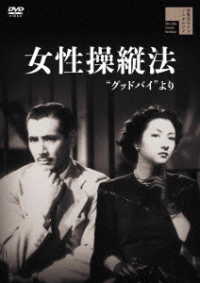
- DVD
- 女性操縦法“グッドバイより”






