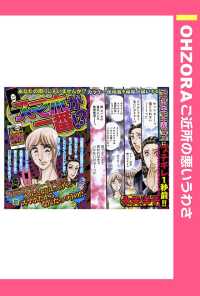目次
不登校・ひきこもり問題の構造とそれを捉える三つの視点
「社会」から捉える不登校・ひきこもり問題
「親」から捉える不登校・ひきこもり問題
「当事者」から捉える不登校・ひきこもり問題
「支援団体・関係機関」から捉える不登校・ひきこもり問題
著者等紹介
中原恵人[ナカハラシゲト]
1970年5月22日生まれ。茨城県つくば市在住。筑波大学在学中から、政治・教育・農業・ライブハウス経営と様々な活動を展開するも、そばにはいつも音楽と詩と子供達が。現在もNPO法人『Future School*燦*』理事長として「不登校・ひきこもり」の子供達と日々共に過ごしながら、創作体現チーム「Ryu‐NOS’~りゅうのす」を率い、精力的に音楽・執筆・講演活動を行っている
伊藤哲司[イトウテツジ]
1964年5月19日生まれ。茨城県水戸市在住。茨城大学人文学部教授として社会心理学の研究・教育にあたっている。1998~1999年のベトナム・ハノイでの在外研究をきっかけに、戦争や平和の問題、学校教育における子どもの問題、持続可能な社会をどう作っていくのかというサスティナビリティ学の問題などに意欲的に取り組んでいる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
安土留之
1
著者は、3つの視点で引きこもりを考えることが重要だという。引きこもり本人のミクロの視点。社会のマクロな視点。そして、家族、学校、友人関係などの中間のメゾの視点。 引きこもりという言葉の流布により、安易にひきこもりをしてしまう子どももいるという。症名をつけることが症状拡大を産むという逆説。 本書に明確な答えはない。ただ、冒頭の詩の一節「僕らはそこに生きるだけ」こそが本人が決意すべきことであり、末尾の一節「一度つないだ手と手を、決して離したりはしません」が周囲の人間が決意すべきことなのだろう。2024/11/08
ひろとん
0
NPO法人*燦*の代表中原恵人と社会心理学者の伊藤哲司の講演会の記録。最終章に書かれていた、行政の対応に我慢しながら委託事業をしている話が興味深い。伊藤哲司が心のノート、並びに河合隼雄を批判し、「心の問題」として扱うことの危険性を示唆しているのは好感。ユートピアである*燦*から「社会参加」へのプロセスが細かくは記載されていなかったので気になる。2017/08/12