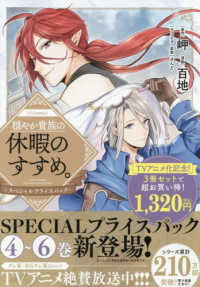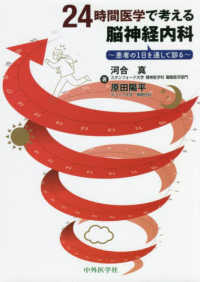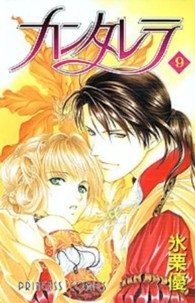内容説明
画一的・一方的な授業になりがちな「個別最適化の時代」。そうした時代に、多様な子どもたちをつなげるために教師はどんな問いを投げかければよいのか。研究者たちの理論と、現場教師たちの実践から、これからの「発問」を提案する。
目次
プロローグ 授業で「問う」ことの現在―個別最適化の問題
1 発問の考え方(発問の哲学(フィロソフィ)と技術(タクト)
教材研究と発問
発話の場づくりとしての発問)
2 個別の学び、協働の学びと教師の問いかけ(学習集団づくりの授業;一人ひとりの学びから生まれる「問い」と学び合う中で生まれる「問い」)
3 探究学習と教師の問い(探究学習において教師が問いかけることの意味;学びを育てる教師の役割とは何か―「自主探究的な学び」の授業実践から)
4 争点のある学びと教師の問い(市民性教育としての話し合い:個人の問題から学校全体の生活課題へ;SDGsに関する学習の要点と教師に求められる役割や工夫)
5 子どもの多様性と学び(子どもたちの特別な教育的ニーズを保障する教師の発問;性の多様性をめぐる学びと教師の問いかけ)
エピローグ 個別最適化の時代に教師であることの意味
著者等紹介
竹川慎哉[タケカワシンヤ]
愛知教育大学教育学部准教授。1978年、岐阜県生まれ。名古屋大学大学院教育発達科学研究科博士課程後期課程修了。博士(教育学)。中部大学現代教育学部幼児教育学科を経て現職。専門は、教育方法学、カリキュラム論
豊田ひさき[トヨダヒサキ]
朝日大学教職課程センター教授・大阪市立大学名誉教授。1944年、三重県生まれ。広島大学大学院教育学研究科修士課程修了。教育学博士。大阪市立大学大学院文学研究科教授、名古屋大学大学院教育発達科学研究科教授、中部大学現代教育学部初代学部長等を経て現職。専門は、教育方法学、カリキュラム論、授業実践史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
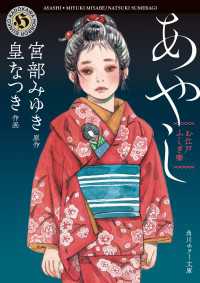
- 電子書籍
- お江戸ふしぎ噺 あやし 角川ホラー文庫