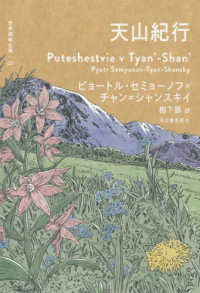内容説明
愛着の問題、認知の歪みがある子、発達障害、ギフテッド、外国にルーツのある子…多様な子どもたちが教室で過ごしている中、一斉一律に揃える授業・学級づくりでは、もう通じなくなってきている(指導が入っていかない)のではないだろうか。教室の多様性にどう対応していけばいいのか。そもそも揃わない、多様性を前提とした授業・学級づくりをさまざまな視点から問う!
目次
巻頭座談会 揃わない前提で共に生きるということ(米澤好史×青山新吾×稲井咲紀×小島章子)
巻頭言 これまでの授業・学級づくりが通じなくなってきている(石川晋)
1 教室の多様性にどう対応するか
2 揃わない、多様性を前提とした授業・学級づくり
座談会 チームで多様な子ども・保護者と関わる―学校が楽しい、居心地のいい場所となるために(内藤愼治×在川彩子×大谷舞×堀井智帆)
特別企画 第21回学事出版教育文化賞 優秀賞受賞論文 情緒障害児教育における「児童が納得できる」規則の指導―応用行動分析学の行動制御技法を用いた朝の会の訓話(河村優詞)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ムーミン
27
タイトルに惹かれて購入。理論的にはいろいろ言われていることが大半でしたが、いずれも実践や経験から実感したことが、借り物ではないそれぞれの方の言葉で書かれていたので、そこがよかったです。特別企画の受賞論文は参考になります。2024/06/26
ムーミン
14
要点をまとめました。2024/07/05
2h35min
3
これはかなり示唆深い内容だった。専門家も現場の教員も、考え方は近かった。システムそのものに無理があるが、現場では今できることをするしかない。2025/06/29
かるー
3
教師集団の若年化はベテランの先生に揃えることである程度守られてきた。しかし、本書にもあるこれまで通りの指導や学級経営が通用しない時代に入った今、それも厳しくなっているんだと感じる。揃えるところ揃えないところの取捨選択の難しさはもちろんあるが、本書のタイトル通り揃わない前提を教師自身が持っておくのは大切なんだと思う。そして、揃わない要因について様々な視点から知識として知っておく必要も感じた。2024/07/17
あべし
3
私は講師時代に2年間通級を担当したことがある。この2年間は本当に貴重な2年間だった。特別支援学級とも交流があったからだ。ここに通ってくる子どもは、本当に「できない」のだ。だから、通常級で担任をした時、この時の経験は大きな財産となった。しかし、このような特性を持った子が数多くいる学級をもった時、ここで学んだ経験が全くいきなかった。「揃わない前提」であることはもはや当たり前だ。しかし、だからと言ってその行為を許容することは、集団としての力が発揮されない。そういう子たちも含めて、どうやって束ねていくか。2024/03/30