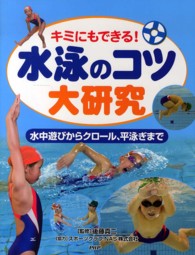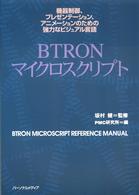内容説明
楽しいクラスをつくるためには、ちょっとした技術が要る。ただ単に教室でギャグをとばすことでも、ネタで笑わせようとすることでもなく、日常の中で、子どもたちをよく観察して適切な言葉掛けをしたり、子どもの失敗をリカバリーしたりするような発想とアイデアが大切だ。シリーズ第2弾の「子どもを面白がらせるワザ」では、教師側からの工夫や言葉掛け、子どもの姿に適宜対応する技術を伝授。
目次
第1章 ネタではなく日常が大切(子どもたちの笑顔を見るために;強い薬には副作用がある ほか)
第2章 授業をちょっと楽しくする(楽しいネタをする前に、心がけておくこと;挨拶 ほか)
第3章 失敗を生かす(失敗を笑わないのではなく…;子どもを笑いものにすることではない)
第4章 小道具を用意する(スタジオをつくっちゃえ;僕の教室にあったグッズ ほか)
第5章 お帰りのとき(「サヨウナラ」にこだわろう!;帰りの会はシンプルに ほか)
著者等紹介
多賀一郎[タガイチロウ]
1955年兵庫県生まれ。追手門学院小学校講師。神戸大学附属住吉小学校を経て私立小学校に長年勤務。元日本私立小学校連合会国語部全国委員長。保護者のために「親塾」を開催したり、若手教師育成のために全国各地のセミナーで登壇したり、公・私立小学校にて指導助言を行っている
俵原正仁[タワラハラマサヒト]
1963年兵庫県生まれ。兵庫県芦屋市立山手小学校校長。兵庫教育大学卒業後、兵庫県公立小学校教諭として勤務。教材・授業開発研究所「笑育部会」代表(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
家主
U-Tchallenge