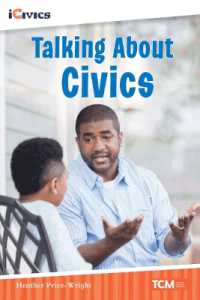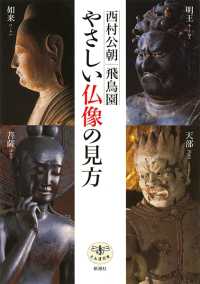内容説明
分かりやすい理論解説と実践分析で、「変わる学校」「思いを実現する学校」「先生がいきる学校」を目指して、学校で“今できること”を提案します。妹尾学校マネジメント論の基本シリーズ!
目次
第1章 教職員を動かすにはなにが必要か―モチベーション・マネジメントのススメ(どんなときに先生たちの心に火が付くのか?;人材育成の悪循環とフィードバックの技術)
第2章 あなたの学校は“チーム”になっているか?(学校が“チーム”となるには;教頭はつらいよ)
第3章 忙しすぎる学校―働き方改革はなんのため?(相互不干渉な職場―多忙化と個業化のなかで;教師の過労死を二度と起こさないために;半径3メートルからの業務改善・働き方改革;この20年間、学校の長時間労働に、わたしたちはなにをしてきたのか;“ブラック部活”をどうするか―多忙とやりがいとの葛藤、自由と規制の振り子)
著者等紹介
妹尾昌俊[セノオマサトシ]
教育研究家、学校マネジメントコンサルタント。京都大学大学院修了後、野村総合研究所を経て、2016年から独立。文部科学省、全国各地の教育委員会・校長会等で、組織マネジメントや学校改善、業務改善、地域協働等をテーマに研修講師を務めている。学校業務改善アドバイザー(文部科学省、埼玉県、横浜市ほか)、中央教育審議会「学校における働き方改革特別部会」委員、スポーツ庁ならびに文化庁において、部活動のガイドラインに関する有識者会議の委員も務める。NPO法人「まちと学校のみらい」理事としても活躍(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
saiikitogohu
Kaori
ポッポ
どこかの国語教師
-

- 和書
- 季刊 労働運動 28