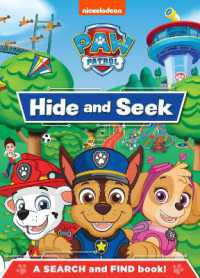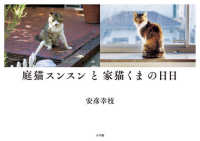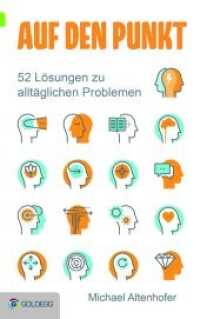内容説明
ボディパーカッションは、言葉ではなく身体を使って手拍子、お腹をたたく、膝を打つ、足ぶみ、ジャンプ、お尻をたたくなど身体の様々な所をたたいて音や動作で表現し、グループや全体で合わせたり、即興的にアンサンブル(身体表現方法の様々なくみあわせ)をつくり上げたりする活動。ペアやグループで身体表現をし、お互いの個性や表現を認めあうなかで、次第に子どもたち同士でコミュニケーションを取りあうようになっていき、教室が笑顔の花束で満ちていきます。
目次
ボディパーカッションでどの子も表現力が高まる!―準備編(なぜ、ボディパーカッションで表現力が高まるのか;ボディパーカッションは、音がずれても大丈夫;ボディパーカッション教育は「音が聞こえなくても、楽譜が読めなくても」楽しめる;特別支援学校、特別支援学級で行う際の指導のポイント ほか)
ボディパーカッションをやってみよう!―実践編(みんな集まれ!「リズムでタタタン」;ものまね上手になれるかな?「まねっこリズム」;集中力を発揮して!「ハンカチリズム」;先生との対話が重要!「手拍子リズム名人」 ほか)
著者等紹介
山田俊之[ヤマダトシユキ]
福岡県久留米市立久留米特別支援学校教頭。九州大学大学院人間環境学府教育システム専攻修士課程修了。ボディパーカッション教育研究会代表。1986年小学校4年生を担任し、友達同士でリズムアンサンブルを創り上げる「ボディパーカッション教育」を考案。その後、小学校、特別支援学校(知的障害・肢体不自由)、不登校施設等でボディパーカッションの実践指導を重ねる。2009年第44回NHK障害福祉賞最優秀賞を受賞。2011年第60回読売教育賞最優秀賞(特別支援教育部門)を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。