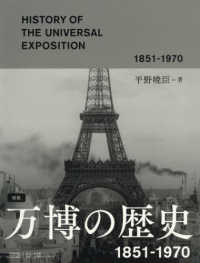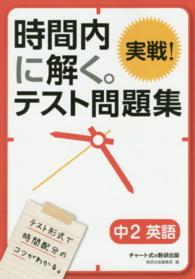目次
第1章 理論編(子どもと共につくるパフォーマンス課題;指導に生かすルーブリック;他領域にパフォーマンス評価を生かす)
第2章 実践編(子ども自身が学ぶ価値を実感することができるパフォーマンス課題を設定する;パフォーマンス課題が子どもの問題となる過程を重視した状況づくりをする;質的転換点に着目して指導に生かすルーブリックをつくる;ルーブリックの共有により子どもの豊かな問題解決を促す;多様な評価により子どもの認識と行動の統一を促す;探究する姿の評価を通して、自ら学び自ら考える子の育成を目指す;表出させたい姿を明確にし、外国語に主体的に取り組もうとする態度を養う)
著者等紹介
田中耕治[タナカコウジ]
京都大学大学院教育学研究科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
はばたき
0
私たちの学校の研究図書、新刊。パフーマンス評価を手がかりに取り組む、子ども主体の学習を、全国の教師仲間と一緒に作り上げていきたいと考えています。 2013/01/19
たか
0
新任校で同僚にパフォーマンス課題について教えてもらい3ヶ月程実践してきた。改めて、理論的に理解することができた。 ・パフォーマンス課題を設定 →3要素「学習の目的」「学習方法・道筋」「表現方法」 →子どもの疑問や関心から作り、子どもと共に修正していく →個別最適、協同どちらの要素も含めた課題にする ・ルーブリックの必要性 →その課題に限定したものではなく汎用性のあるものに →ルーブリックがあることで子どもの学習の道筋も見える。 →A B Cの具体的な子どもの姿をイメージしておく。 2022/07/30
-

- 電子書籍
- KATSU!(4) 少年サンデーコミッ…