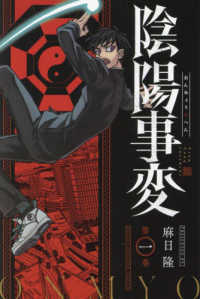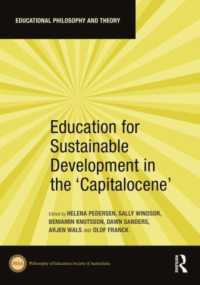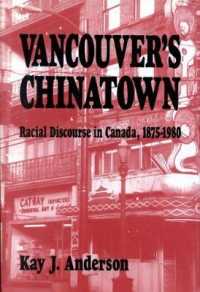内容説明
原発に頼らない温暖化防止、CO2を減らす地域活性化。地域が自立するのに必要な政策、産業、エネルギー、人材とは―。
目次
第1部 なぜ地域で温暖化対策が必要なのか(世界と日本の温暖化対策;自治体による温暖化対策;地域づくりを視野に入れた温暖化対策;温暖化対策における地域資源とは)
第2部 国内外の先進事例に学ぶ(NPO地域づくり工房(長野県大町市)―小水力、菜の花等を活かした仕事おこし
温泉観光地―サステイナブルツーリズムを目指して
高知県梼原町―森の恵みを活かした地域づくり
岩手県葛巻町―エネルギーと食料自給の地域づくり
滋賀県野洲市―地域通貨による地産地消の仕組みづくり
富山市―公共交通を賢く使うコンパクトシティ
京都市―パートナーシップで築く低炭素都市
ドイツ―再生可能エネルギーによる農村活性化
アメリカ―再生可能エネルギーによるコミュニティ再生)
第3部 地域を活性化する温暖化対策を考える(温暖化対策と地域活性化が成功する条件;地域資源を活用する温暖化対策の推進)
著者等紹介
和田武[ワダタケシ]
日本環境学会会長、自然エネルギー市民の会代表。1941年生まれ。京都大学大学院工学研究科修士課程修了。工学博士。住友化学工業中央研究所、愛知大学等を経て、1996年立命館大学産業社会学部教授、2006年特別招聘教授(2008年退職)。専門:環境保全論、資源エネルギー論
新川達郎[ニイカワタツロウ]
同志社大学大学院総合政策科学研究科教授。1950年生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科博士後期課程満期退学。修士(政治学)。財団法人東京市政調査会研究員、東北大学大学院情報科学研究科助教授等を経て現職。専門は行政学、公共政策論、地方自治論
田浦健朗[タウラケンロウ]
特定非営利活動法人気候ネットワーク事務局長。名古屋学院大学大学院非常勤講師。神戸大学大学院国際協力研究科修士課程修了。1997年のCOP3をきっかけに地球温暖化問題に携わる。1998年から現職として、温暖化問題に関する調査・研究、政策提言等を行う
平岡俊一[ヒラオカシュンイチ]
北海道教育大学教育学部釧路校講師。1978年生まれ。立命館大学大学院社会学研究科博士課程後期課程修了。博士(社会学)。特定非営利活動法人気候ネットワーク研究員、龍谷大学LORC博士研究員を経て2010年より現職。地域・自治体での温暖化対策、市民参加・パートナーシップなどが専門
豊田陽介[トヨタヨウスケ]
特定非営利活動法人気候ネットワーク主任研究員。立命館大学非常勤講師。1977年生まれ。立命館大学大学院社会学研究科博士課程前期課程(環境保全研究室)修了。社会学修士。市民による温暖化防止に関する調査、研究、各地の自然エネルギー事業へのアドバイス・サポートを行う(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
壱萬参仟縁
Satoshi Murai