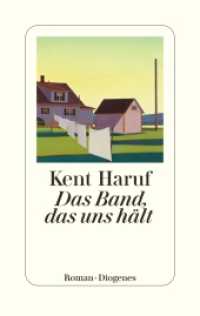出版社内容情報
社長就任後、わずか5年で利益を15倍にした著者が明かす経営戦略。会社と社員を劇的に変え、好業績を生む具体的な施策を公開。
内容説明
極限まで効率を求める「生産性至上主義」の経営は、従業員を「コスト」と考え、疑う経営だと言えます。これでは、従業員はただ言われたことを効率よくこなすだけの存在となり、助け合うことも、人の役に立とうとすることもなくなります。そう考えると、「人」を中心に物事を考える経営は当たり前のことではないでしょうか。そして、それを実践するためには、従業員を心の底から信じることが不可欠なのです。
目次
第1章 モチベーションの源泉は「人の役に立てること」―「助け合う社風」はどのように生まれたのか?(なぜ、宮田運輸には「助け合う」社風が根づいたのか?;「助け合う」社風こそ、会社にとって最も重要な資産 ほか)
第2章 1人ひとりを信じて任せる―従業員の主体性を生みだす仕組み(人をとことん信じる会議「みらい会議」とは?;参加者が涙する会議、みらい会議で行われていること ほか)
第3章 リーダーに最も必要なのは「愛」―人をとことん信じ切る「心の経営」(リーダーは「愛」がなくては務まらない;従業員を性悪説で管理しない ほか)
第4章 目先の数字は絶対に追わない―目の前の困っている人を助け続ければ、会社と従業員は成長する(父からの教えの裏にある「困った人がいたら助ける」の精神;信用を築くためには、とにかく運ぶこと、助けること ほか)
第5章 人は「管理」ではなく「幸せ」になってこそ成長する―従業員と社会を幸せにするプロジェクト(「こどもミュージアムプロジェクト」のはじまり;子どもの絵を「背負う」と運転がやさしくなる ほか)
著者等紹介
宮田博文[ミヤタヒロフミ]
1970年大阪府生まれ。高校卒業後、祖父が創業した宮田運輸に入社。運転士、専務などを経て2012年社長に就任。社長就任当初、従業員に対する管理を強め、数字を上げようとしたことが引き金となり、死亡事故が発生。そこから方針を大転換。現在は、従業員をとことん信じる「心の経営」をモットーとしている。2007年、稲森和夫氏が主宰する経営塾「盛和塾」に入塾。死亡事故をきっかけに同社がはじめた、トラックに子どもの絵をラッピングして、事故抑止につなげる仕組み「こどもミュージアムプロジェクト」は、現在150社以上の企業が参加。また、同社が行っている、すべての従業員、社外の人誰もが参加できる経営会議「みらい会議」には、全国各地から数多くの人が参加している。メディア出演多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
清游@草ぶえの丘で森林浴♨︎
Takateru Imazu
満天
Koji Takai
-

- 電子書籍
- T子の一発旅行【単話】(2) FC J…