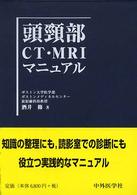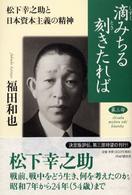内容説明
本書は、戦後における子どもの暮らしの変容過程をたどり、その生活世界の著しい変貌をイメージ豊かに描きだした。教育の社会史の新しい試みである。まず1903年代の子どもの暮らしをふり返ることからはじめ、敗戦直後、そして1960年代の高度経済成長期を経て現在にいたるまでの、波乱にとんだ歩みを六章に区分けし、それぞれの時期に特徴的な子どもの暮らしぶりを浮き彫りにしていく。
目次
序章 子どもの「暮らし」の社会史―戦後の子どもの生活世界の変容過程をたどる
第1章 子どもの「暮らし」―戦前と戦後(1930年代~45年)
第2章 戦後社会と子どもの「暮らし」(1945~50年代)
第3章 高度経済成長期の子ども(1960年代)
第4章 情報化社会と「暮らし」の変容(1970年代)
第5章 「学校化社会」と子ども(1980年代)
終章 子どもの「暮らし」の現在―「豊かさ」の中の生活喪失(1990年代)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mine
1
せつなくなる程うつくしい。/晩春の日には、連綿と連なるれんげ畑のただなかで、夕刻まで、一、二本あるかなきかの、白れんげを探した。(…)その一輪の高貴な白いれんげ草は、私の人生すべての希望とあこがれを集約しているように思われた。紅蓮の果てしないれんげ畑で、突然変異の白いれんげの花を探す、子どもの日の私自身を心に描くとき、私は、その、赤と白のコントラスト、無限の赤い花冠と、ただ一輪の純白の花冠の対比とともに、子どもの日の私の、気高く希少なるものへの、その壮烈なあこがれにいい知れない感動を覚えるのである。2021/12/14
-

- 電子書籍
- オメガ・メガエラ(1)