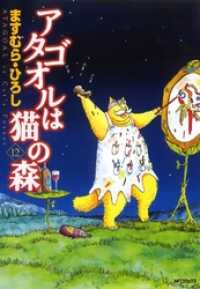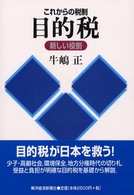- ホーム
- > 和書
- > 教育
- > 特別支援教育
- > 知的障害・発達障害等
出版社内容情報
発達障害のある子の持つ感覚特性(過敏・低反応など)や不器用さ(発達性協調運動症など)の理解と支援について具体的に紹介する。
目次より
第1章 発達障害のある子どもの感覚と運動の問題…岩永竜一郎
第2章 感覚について考える―当事者の視点から…小道モコ
第3章 自閉スペクトラム症の感覚の問題の背景…井手正和
第4章 感覚処理特性のアセスメント…萩原 拓
第5章 感覚面の問題への支援…加藤寿宏
第6章 協調運動に関する日常の困りごと…笹森理絵
第7章 発達性協調運動症(DCD)の特徴と支援の動向…岩永竜一郎
第8章 協調をアセスメントする意義―DCDQ,M-ABC2日本語版の開発と臨床応用
…中井昭夫
第9章 協調運動のアセスメント―質問紙と個別検査…岩永竜一郎
第10章 協調運動面の問題への支援―CO-OPを用いた実践…塩津裕康
第11章 不器用さのある子どもへの日常生活での支援―遊び・生活動作・学習
…池田千紗
目次
第1章 発達障害のある子どもの感覚と運動の問題
第2章 感覚について考える―当事者の視点から
第3章 自閉スペクトラム症の感覚の問題の背景
第4章 感覚処理特性のアセスメント
第5章 感覚面の問題への支援
第6章 協調運動に関する日常の困りごと
第7章 発達性協調運動症(DCD)の特徴と支援の動向
第8章 協調をアセスメントする意義―DCDQ、M‐ABC2日本語版の開発と臨床応用
第9章 協調運動のアセスメント―質問紙と個別検査
第10章 協調運動面の問題への支援―CO‐OPを用いた実践
第11章 不器用さのある子どもへの日常生活での支援―遊び・生活動作・学習
著者等紹介
柘植雅義[ツゲマサヨシ]
筑波大学人間系障害科学域教授。愛知教育大学大学院修士課程修了、筑波大学大学院修士課程修了、筑波大学より博士(教育学)。国立特殊教育総合研究所研究室長、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)客員研究員、文部科学省特別支援教育調査官、兵庫教育大学大学院教授、国立特別支援教育総合研究所上席総括研究員・教育情報部長・発達障害教育情報センター長を経て現職
岩永竜一郎[イワナガリョウイチロウ]
長崎大学生命医科学域(保健学系)教授、長崎大学子どもの心の医療・教育センター副センター長、長崎大学大学院医歯薬学総合研究科(博士課程)修了(医学博士)。認定作業療法士、公認心理師、感覚統合認定講師、特別支援教育士スーパーバイザー、自閉症スペクトラム支援士エキスパート。発達障害児に見られる感覚や運動の問題に関する研究や支援を行っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
happy55703
じゃがたろう