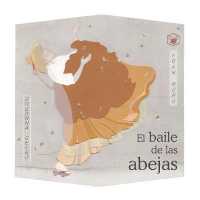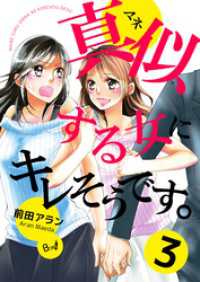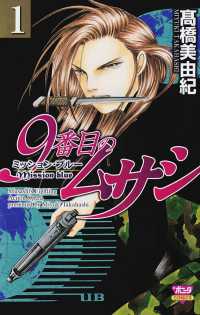内容説明
ヒトというシステムの動作原理の解明をめざすユニークな研究の成果。二足歩行はなぜ可能なのか?乳児の発達はなぜU字型をたどるのか?脳と身体のダイナミクスを、非線形力学・制御理論・脳神経生理学・発達心理学の領域を横断しながら考察する。
目次
1章 運動と自己組織(生きている状態としての運動;自己組織現象としての運動;制御として見た運動;運動の生理学)
2章 歩行における脳と環境の強結合(グローバルエントレインメント(global entrainment)
ヒトの歩行の再現
合目的性と自己組織性)
3章 身体の自由度問題と脳のバインディング問題(運動における自由度の凍結(freezing)と解放(freeing)
脳における同期と非同期)
4章 初期発達過程におけるU字型現象(運動の分化と統合;乳児の視覚世界;運動感覚統合のU字型現象)
5章 脳と身体のデザイン原理
著者等紹介
多賀厳太郎[タガゲンタロウ]
東京大学大学院教育学研究科講師。1965年生まれ。神奈川県出身。東京大学大学院薬学系研究科博士課程修了、博士(薬学)取得。京都大学基礎物理学研究所学振特別研究員、ボストン大学神経筋研究所博士研究員、東京大学大学院総合文化研究科相関基礎科学系助手を経て現職。カリフォルニア工科大学ヒューマンフロンティアサイエンスプログラム短期フェロー、科学技術振興事業団さきがけ21研究員などを併任
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
人生ゴルディアス
3
誠実な学者先生が、慎重にわかっていることとわかっていないことを丁寧に教えてくれる感じに非常に好感が持てる。人型ロボット系で、いつも大袈裟に成果を吹聴している黒尽くめの教授は見習うべきでは…。歩行という行為が大域引き込み等、微分方程式で求められる話とか、U字型の運動とか、面白い。また、赤ん坊の運動の発達から、人間はどうやら何でもできる状態で生まれ、少しずつ制御を覚えていくらしい。人間らしさとは、何かをできることにではなく、なにかをしないことにある、という箴言は正しいようだ。2018/11/23
gachin
2
とても読みやすい。/ 歩行速度を上げたときと下げたときでは、歩容の転換点速度が異なるらしい(ヒステリシス)。歩行速度が中脳歩行野での刺激強度に還元できるのであれば、必ずしも歩容には脳内表象は関わっていない、とのこと。/ 歩行周期の揺らぎは疾患や老化で白色ノイズになる。/ 認知に関しては僕自身ピアジェ的な構成主義に傾倒してたけど、実情は(ギブソン的に)生得的統合を外界との相互作用で再編成しているようだ。/ 自分の体であれば除脳カエルでもリーチングができる。2021/03/18
ざきさん
2
10年くらい前に買って読んだ本だったが再読。当時、まだ療法士として若い頃、ICIDHは既に否定されていたのに「障害があるから生活に支障が出ている、障害を治せば良い」一辺倒の療法士業界に疑問を呈したどり着いたのが環境心理学だった。障害があれば生活できないのか?治らなければ幸せになれないのか?この疑問に対して障害ベースのボトムアップでは答えにたどり着かない。そして現在、未だにリハビリ界は機能回復ばっかりやっている。僕の違和感は続く…しかし、この違和感を大切にする事が答えに近付くのだと信じよう。2020/11/15
T2C_
1
様々な運動の創発を、主に乳幼児の挙動から見つめる一冊。正直な所あまり琴線に触れなかったというか食指を動かされなかったというか。2002年初出版と少し古い事もあるが、概括すれば「難しい。かなり限定的な範囲で実験してみた。その内の少しの事しかわからなった。」という事を言っているだけという印象を受けた。難度からして当然と言えば当然なのだが、次にこういった類のものを読む時はもう少し具体性と先見性に富んだものを選ぼうと思う。2015/08/19
andaseizouki
0
運動制御について独自の理論を展開し、どのように能力を体得していくか赤ちゃんの実験での結果をメインに書いている。専門用語も多いが、読んでいてわくわくするそんな一冊。関連の文献もたくさん紹介されているので、参考にしたい。2016/12/08