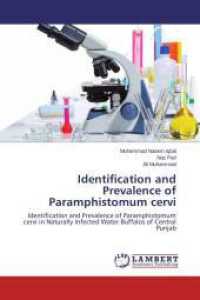出版社内容情報
医療、福祉、教育、産業などの現場で対人援助に従事する人のためのスキルを伝える。援助とは何か? 援助者が持つべき資質・スキルとは? 行動の変化をもたらす方略とは?医療,福祉,教育,産業などの分野で活躍する対人援助職にとって必須である,ヘルピングのスキルを,援助者と相談者の関係性に焦点をあて,実践的に解説する。・幅広い内容 *日常的な援助から,悲嘆や危機介入まで扱っています。・初学者に *援助者が知っておくべき基本的な事柄をおさえています。・中級以上の援助者に *様々なトピックについて深く学ぶツールとして役立ちます。・確実に学ぶために *各章ごとに,結果のセルフチェックができます。
序文
第1章 援助:その意味について
あなたの援助に対する見方は?
援助過程
相談者の成長を促す
責任
同意に基づいた援助
援助者のニーズに沿うということ
全人的健康と至高の機能性を求める
動機:援助者になるべきか否か
社会貢献/サービスの精神/援助者の問題解決と関連した援助/熟達者になる
科学か? アートか?
援助の効力
プロフェッショナルとパラプロフェッショナル
コミュニティ援助
ピア援助と世代間援助
自助グループ
援助者が得るもの
援助とは自助のための対処スキルを獲得させること
理解、支援、活動の援助スキルモデル
2段階の援助モデル/スキルの分類
より深く学ぶために
第2章 援助者の特徴
なぜ援助が人々の成長の助けになるのか?
援助者の機能レベルとそのスタイル
援助と援助者のライフスタイル/援助者と相談者の相性/成長を促進する役割としての援助者
援助者の性格
援助者の性格特徴/学者‐研究者としての援助者
結論
より深く学ぶために
第3章 援助過程
関係
関係における次元
経験としての援助過程
援助過程の段階
段階1:開始 /専門的な関係を開始する/段階2:明確化 /段階3:構造/段階4:関係/段階5:探索/段階6:統合/段階7:計画立案/段階8:終結
段階的に考えることについてのジレンマ
より深く学ぶために
第4章 理解のための援助スキル
スキル訓練の理論的な根拠
スキルのタイプ1:聴くこと
寄り添うこと/言い換えること/明確にすること/現実検討
スキルのタイプ2:導くこと
質問/間接的な導き/直接的な導き/焦点化
スキルのタイプ3:反映
感情の反映/経験の反映/内容の反映/反映技法の典型的な誤り
スキルのタイプ4:挑戦
援助者の感情を認識する/感情を説明し共有する/フィードバックと他者からの意見/自分に挑戦する
スキルのタイプ5:解釈
解釈的な質問/空想と隠喩による解釈/解釈のレベル
スキルのタイプ6:情報提供
情報提供/助言
スキルのタイプ7:要約
より深く学ぶために
第5章 喪失と危機における援助スキル
問題となる人的状況
人生の転機/家族の危機
言葉の定義
ストレス/危機/支援/希望と絶望/強烈な悲嘆
危機的状況での援助方法
危機介入のステップ/多面的支援/希望の形成と維持/回復と成長の方略/危機センター/社会復帰訓練施設/治療センター/治療的なカウンセリング方略/なぐさめるという技術
支援と危機管理のためのスキル
間接的に触れ合うスキル/安心を与えるスキル/リラックスさせるスキル/中心化のスキル/代替案の構築/紹介するスキル/支援システムの刷新または構築/予防
より深く学ぶために
第6章 積極的活動と行動変容の援助スキル
援助に対する行動的アプローチ
特徴とモデル/応用
問題と目標
問題は目標に変化する/目標設定における困難/目標達成とその後
問題解決、意思決定、計画立案
論理的問題解決過程/論理的問題解決に求められるスキル/直観的問題解決におけるスキル
行動変容
行動変容法の前提/行動変容方略/モデリング/報酬スキル/消去スキル/契約スキル/嫌悪コントロール法を用いたスキル/脱感作法を用いたスキル
より深く学ぶために
第7章 援助関係における倫理的問題
倫理とは何か?
法律と倫理の違い
援助者のセルフケア
倫理と対人関係
多重関係/相談者との身体的接触
援助者の能力と限界
インフォームド・コンセント
緊急・危機における対応
より深く学ぶために
第8章 援助過程についての考察
道しるべとしての理論
個人的な理論の有用性
理論を構築する/援助理論の有用性と限界
援助過程の一般的理論
折衷/統合系の介入法/精神分析系の介入法/現象学系の介入法/行動主義系の介入法/論理・認知療法系の介入法/コミュニケーション系の介入法/ライフスタイルを通しての介入法/家族療法系の介入法/異文化に配慮した介入法
社会的な問題
価値観の問題/政治的な問題/宗教的な問題とスピリチュアルな問題/経済的な問題:マネージドケアについて/技術的な問題
援助スキルの理論と実践をつなぐ
ニーズ/学習/気づき/コミュニケーション
相談者が変化を見せない時
集団を通しての援助
個人的あとがき
より深く学ぶために
文献
訳者あとがき
人名索引
事項索引
ローレンス・M・ブラマー[ブラマーローレンス エム]
著・文・その他
ジンジャー・マクドナルド[マクドナルドジンジャー]
著・文・その他
堀越 勝[ホリコシ マサル]
監修/翻訳
内容説明
援助とは何か?援助者が持つべき資質・スキルとは?行動の変化をもたらす方略とは?医療、福祉、教育、産業などの分野で活躍する対人援助職にとって必須である、ヘルピングのスキルを、援助者と相談者の関係性に焦点をあて、実践的に解説する。
目次
第1章 援助:その意味について
第2章 援助者の特徴
第3章 援助過程
第4章 理解のための援助スキル
第5章 喪失と危機における援助スキル
第6章 積極的活動と行動変容の援助スキル
第7章 援助関係における倫理的問題
第8章 援助過程についての考察
著者等紹介
堀越勝[ホリコシマサル]
国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター研修指導部長。米国のバイオラ大学で臨床心理学博士を取得、マサチューセッツ州のクリニカルサイコロジストのライセンスを取得。ハーバード大学医学部精神科においてポストドク及び上席研究員として、ケンブリッジ病院の行動医学プログラム、マサチューセッツ総合病院・マクレーン病院の強迫性障害研究所、サイバーメディシン研究所などで臨床と研究を行う。2000年に帰国し、筑波大学大学院人間総合科学研究科(講師)、駿河台大学心理学部(教授)を経て現職
大江悠樹[オオエユウキ]
筑波大学大学院人間総合科学研究科ヒューマン・ケア科学専攻3年制博士課程在学中。臨床心理士。とくに人間の感情に関心を持っており、現在は嫌な気持ちに耐える力「不快情動耐性」について研究を行っている。調査と実験を組み合わせ、この概念について実証的な研究を行うことを目指している
新明一星[シンメイイッセイ]
国立精神・神経医療研究センター、認知行動療法センター所属の研究員。臨床心理学修士(駿河台大学大学院心理学研究科臨床心理学専攻修了)。死別や喪失に対する悲嘆研究から、認知行動療法を用いてのパーキンソン病患者の不安とうつに対しての介入及びパニック障害などの不安症への精神療法を実施している。治療効果を高める上で必要とされる患者との関係の構築、及び、コミュニケーションスキルに関心を持ち、心理療法の実践的側面の研究を行っている
藤原健志[フジワラタケシ]
筑波大学大学院人間総合科学研究科ヒューマン・ケア科学専攻3年制博士課程在学中。臨床心理士。青年期の社会的スキル、とくに人の話を「聴くスキル」について研究している。青年を対象に、聴くスキルと適応感との関連を、発達心理学・臨床心理学の観点から研究している(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 半導体デバイスの物理