- ホーム
- > 和書
- > 教育
- > 教育問題
- > いじめ・非行・不登校・引きこもり
出版社内容情報
不登校に関する臨床心理学の研究を俯瞰し、特徴別に10のケースを解説。スクールカウンセラーの不登校フォーミュレーションも提案。
目次
1. 不登校の理解編
(1) 不登校の現状とその展開
①不登校の定義と現状
②不登校の原因とその過程
③不登校のその後はどうなっているか
(2) 不登校に関する主な研究
①不登校研究の歴史
②不登校に関する臨床心理学における主な研究
1)生徒との1対1の関わり
2)母親面接とそのグループアプローチ
3)発達障害
4)いじめ
5)スクールカウンセラーの職務
6)連携による治療
7)無気力
8)適応指導教室
9)教師による関わり
2. 不登校のケース編
(1) 不登校生徒の特徴別ケース
①分離不安型
②過剰適応(よい子)型
③評価懸念型
④発達障害
1)ADHD
2)アスペルガー症候群
⑤緘黙型
⑥きょうだいでの不登校型
⑦離婚反応型
⑧被虐待型
⑨対抗型
(2) 不登校の方策
①母親面接
②訪問面接
③別室登校
④メールカウンセリング
⑤環境調整
1)いじめ
2)教師の問題
⑥治療機関への紹介
⑦屋外での面接
⑧スクールカウンセラーによる連携
3. 不登校のフォーミュレーション
(1) フォーミュレーションとは
(2) 不登校フォーミュレーションの必要性
スクールカウンセラー用の不登校に関する「フォーミュレーション」
(フォーミュレーション1~13)
注
用語解説
内容説明
臨床経験を生かす!不登校に関する臨床心理学の研究を俯瞰し、特徴別に10のケースを解説。スクールカウンセラーのための不登校フォーミュレーションを提案する。
目次
第1部 不登校の理論編(不登校の現状とその展開;不登校に関する主な研究)
第2部 不登校のケース編(不登校生徒の特徴別ケース;不登校対応の方策)
第3部 不登校のフォーミュレーション(フォーミュレーションとは;不登校フォーミュレーションの必要性;スクールカウンセラー用の不登校に関する「フォーミュレーション」)
著者等紹介
長尾博[ナガオヒロシ]
福岡県北九州市出身。1976年九州大学教育学部卒業。1981年九州大学教育学研究科博士課程単位満了中退。その後、九州大学教育学部助手を経て、活水女子短期大学講師、活水女子大学助教授、活水女子大学教授、現在、活水女子大学特別専任教授、活水女子大学名誉教授。学位;医学博士。専攻;臨床心理学、青年心理学、精神医学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
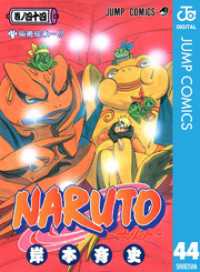
- 電子書籍
- NARUTO―ナルト― モノクロ版 4…







