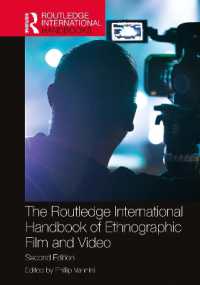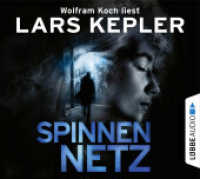出版社内容情報
不登校・学級崩壊・苦戦する学校現場で今こそ求められる「チーム援助」の効果的な進め方を、実証データと具体的実践から示す。子どもに援助を確実に届けるために、教師が自信をもって子どもと向き合うために――苦戦する学校現場で今こそ求められる「チーム援助」とは。その効果的な進め方を、実証データと実践事例から示す。
第1部 データで語る「チーム援助」の必要性
第1章 チーム援助の必要性
1. 子どもの援助ニーズに応じた援助
2. 子どもを取り巻く環境の多様化・複雑化
3. 学校カウンセリングにおける「連携」のかたち
4. 中学生の適応尺度から見たチーム援助の必要性
✎リフレクション
第2章 援助を求める子ども,求めない子ども
1. 子どもは教師やスクールカウンセラーに援助を求めるのか
2. なぜ,子どもは教師やスクールカウンセラーに
援助を求めないのか
3. 教師やスクールカウンセラーに援助を求めやすい子どもは
どのような子どもか
4. 子どもの被援助志向性を高め,援助につなげる試み
5. おわりに
✎リフレクション
第3章 子どもはどうしたらスクールカウンセラーに相談したくなるのか
1. 介入プログラム
2. 測定方法と測定具
3. 結果と考察
4. おわりに
✎リフレクション
第4章 チーム援助を学校に定着させる
――教師の被援助志向性から考える
1. チーム援助に対する教師の意識
2. 何が教師の被援助志向性を高めるのか
3. チーム援助を学校に定着させるための4つのポイン ト
――著者の経験から
✎リフレクション
第2部 チーム援助を核とした学校での援助
第5章 不登校の児童生徒をチームで援助する
1. 不登校についての教師のさまざまな疑問
2. 不登校の類型
3. チームで支援が必要な不登校の典型事例
4. カウンセリングを求めない不登校の子どもとのつながり方
5. チームで取り組む不登校支援の課題
✎リフレクション
第6章 過度な要求をする保護者への対応
1. 現場で何が起こっているのか
2. 保護者とのトラブルにチームで取り組んだ実践事例
3. 保護者との折り合いをよくするために教師は何ができるのか
✎リフレクション
第7章 学級崩壊にチームで取り組む
1. 学級崩壊寸前の小学6年生の学級の事例
2. Q-Uのプロットから見る学級の状態
3. Q-Uのデータの分析を目的とした援助チーム会議の様子
4. 学級の立て直しと個別の支援
5. 援助チーム会議後の学級経営
✎リフレクション
第8章 教師のメンタルヘルス
1. 教師のメンタルヘルスとは
2. バーンアウトに陥らないためには
3. チーム援助と教師のメンタルヘルス
4. おわりに
✎リフレクション
【コラム】
1 適応指導教室
2 不登校に対応すると学級が荒れる?
3 子どもに登校の意志がある場合の不登校児童生徒とのかかわり
4 人的リソース
5 Q-Uとは?
6 認知行動的アプローチ
文献
あとがき
索引
水野 治久[ミズノ ハルヒサ]
著・文・その他
内容説明
子どもに援助を確実に届けるために、教師が自信をもって子どもと向き合うために、今、学校が取り組むべき「チーム援助」とは―実証データと実践事例で解説する効果的な学校カウンセリングの仕組み。学校心理学の具体的展開!
目次
第1部 データで語る「チーム援助」の必要性(チーム援助の必要性;援助を求める子ども、求めない子ども;子どもはどうしたらスクールカウンセラーに相談したくなるのか;チーム援助を学校に定着させる―教師の被援助志向性から考える)
第2部 チーム援助を核とした学校での援助(不登校の児童生徒をチームで援助する;過度な要求をする保護者への対応;学級崩壊にチームで取り組む;教師のメンタルヘルス)
著者等紹介
水野治久[ミズノハルヒサ]
大阪教育大学学校教育講座(心理学教室)教授。筑波大学大学院教育研究科修了、博士(心理学)、学校心理士、臨床心理士。専門は、学校心理学、カウンセリング心理学、異文化間カウンセリング。日本学校心理学会常任理事、『学校心理学研究』編集委員長、日本コミュニティ心理学会常任理事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 人生の鬼・松永安左ェ門