出版社内容情報
「浦河べてるの家」の当事者研究にふれ、どもる人たちが、吃音を受容する生き方の素晴らしさを再確認したワークショップの記録。北海道「浦河べてるの家」の当事者研究にふれることで、どもる人たちが、自分たちの生き方の素晴らしさを再確認できたワークショップの記録。吃音を「治さない」で、「受け入れる」ことのススメ。
「吃音の当事者研究」に寄せて 斉藤道雄
まえがき――吃音という可能性 向谷地生良
? 講演:当事者研究と私 向谷地生良
はじめに――「治さない」というキーワード
1 精神医療の世界で起こっていること
「吃音」の議論の流れは変わる
福祉の中での対立
「保護・管理」から「治療」へ
一九七〇年代、エンパワメントの潮流
私が直面したテーマとメンバーとの共同生活
認知行動療法と協同性
一九八〇年代、薬物療法への傾倒
「リカバリー」の時代へ
2 浦河で、べてるで、行われていること
〈非〉援助の援助=助けないという助け方
当事者研究とは――自分自身でともに
リハビリテーション現象学
二百年研究してもわからない
専門家と当事者の関係の変化
「証」としての当事者研究
当事者研究の実際――統合失調症の影響で顔面へのバッティングに苦労した宮西勝子さんの当事者研究
自由さと自在さがおもしろいところ
3 当事者がもつ力
精神科医も追い詰められている
相談するソーシャルワーカー
ともに無力になる
そんなに幸せにならないから大丈夫
効果があるから広まる
陰の情報は一切伝わってこない
当事者が語ることの重み
解消というかたちでの、生きやすさのための手立て
悩むではなくテーマをもっている
? 講義・演習:当事者研究の実際 向谷地生良
1 講義――当事者研究について
当事者研究の先行研究
「幻聴さんエデュケーションの研究」――どんなときにどんな幻聴さんがくるか
「部屋がどんどん狭くなる」
当事者研究の発想・展開例
2 演習――グループによる当事者研究
土井香緒里さん当事者研究――「土井式緊張ダイエット法」
横田洋子さん当事者研究――「人と比べるモード」の研究
黒崎明志さん当事者研究――「どもれない、どもりの研究」
グループでの当事者研究の振り返り
3 質 問
当事者研究の誕生
自分自身でともに
受容的な傾聴から、対話的な傾聴へ
場をダイナミックにつくっていく聴き方
自己と過去の経験に学ぶ
? 対談:当事者研究を吃音に生かす 向谷地生良・伊藤伸二
はじめに
1 伊藤伸二の当事者研究
なぜ、吃音に悩み始めたか
悩みの悪循環
なぜ治したかったのか
逃げの人生のはじまり
2 吃音の悩みから解放される道筋
どもる仲間と出会う
必死の治す努力の結果、どもりは治らなかった
なぜ、吃音を治すことをあきらめられたか
どもりながら社会に出て行く
3 どもる人のセルフヘルプグループ言友会の設立
「吃音を治す」から、「吃音とつきあう」へ
当事者研究の芽生え
吃音を治す努力の否定の提起
全国吃音巡回相談会
どもる青年との出会い
吃音者宣言から第一回吃音問題研究国際大会
4 対 談
アメリカ言語病理学との違い
弱さについて
対等性について
? 吃音の当事者研究――吃音が治る、治せるを、あきらめる生き方 伊藤伸二
はじめに――今、選択する時
1 世界の吃音治療の現状
【対談】カナダ・北米の吃音治療の現状について
統合的アプローチ
2 吃音の定義から始める吃音の取り組みの再構築
常識に挑戦する
吃音の常識を変える
定 義
吃音が治ること、治すことのあきらめのすすめ
吃音放置のすすめ
治らないものと考える
吃音とつきあうためのプログラム
3 映画『英国王のスピーチ』の当事者研究
当事者研究
あとがき
日本吃音臨床研究会の紹介
向谷地 生良[ムカイヤチ イクヨシ]
著・文・その他
伊藤 伸二[イトウ シンジ]
著・文・その他
内容説明
「べてるの家」の当事者研究にふれることで、どもる人たちが、自分たちの生き方がどんなに素晴らしいのかを再確認できたワークショップの記録。
目次
1 講演:当事者研究と私(精神医療の世界で起こっていること;浦河で、べてるで、行われていること ほか)
2 講義・演習:当事者研究の実際(講義―当事者研究について;演習―グループによる当事者研究 ほか)
3 対談:当事者研究を吃音に生かす(伊藤伸二の当事者研究;吃音の悩みから解放される道筋 ほか)
4 吃音の当事者研究―吃音が治る、治せるを、あきらめる生き方(世界の吃音治療の現状;吃音の定義から始める吃音の取り組みの再構築 ほか)
著者等紹介
向谷地生良[ムカイヤチイクヨシ]
1955年、青森県生まれ。北星学園大学文学部社会福祉学科を卒業後、北海道日高の浦河赤十字病院におけるソーシャルワーカーとしての勤務(1978~2003年)を経て、北海道医療大学看護福祉学部臨床福祉学科教授、社会福祉法人浦河べてるの家理事。浦河赤十字病院に勤務している頃、統合失調症などをもつメンバー有志と一緒に古い教会を借り受けてともに生活し始める。そのことを通じて、統合失調症などをもつ人たちの経験のなかに豊かな可能性を感じ、「社会復帰から社会進出へ」を旗印に1984年に「べてるの家」を設立し、日高昆布の販売などの起業を通じた自立をめざした活動を展開する
伊藤伸二[イトウシンジ]
1944年奈良県生まれ。明治大学文学部・政治経済学部卒業。大阪教育大学特殊教育特別専攻科修了。大阪教育大学専任講師(言語障害児教育)を経て現在、伊藤伸二ことばの相談室主宰。日本吃音臨床研究会会長。大阪教育大学非常勤講師、言語聴覚士養成の専門学校数校で吃音の講義を担当。小学2年生の秋から吃音に強い劣等感をもち、1965年にどもる人のセルフヘルプグループ言友会を設立するまで吃音に深く悩む。長年、言友会の全国組織の会長として活動するが、1994年に言友会から離脱し、どもる子どもの親、臨床家、研究者などが幅広く参加する日本吃音臨床研究会を設立(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
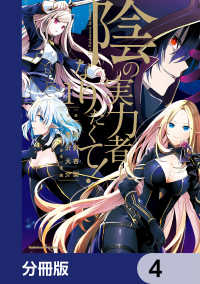
- 電子書籍
- 陰の実力者になりたくて!【分冊版】 4…






