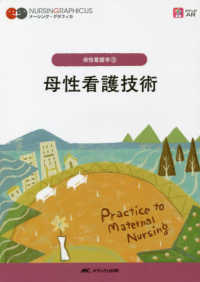出版社内容情報
『家なき子』のフランスでの原典の成立と意味、日本で最初期の作品の翻訳受容の様相を明らかにし、児童文学作品としての源流を探る。フランスの児童文学作品、エクトール・マロ(Hector Malot, 1830-1907)のSans famille(1878)は、『家なき子』の邦題を冠し、日本でもとてもよく親しまれた物語である。
本書は、日本での最初の翻案である五来素川訳『家庭小説 未だ見ぬ親』と、二番目に菊池幽芳による翻訳『家なき児』を研究対象として取り上げ、Sans famille、『未だ見ぬ親』、『家なき児』の三者を考察し、フランスでの原典の成立と意味、日本で最初期の作品の翻訳受容の様相を明らかにすることで、『家なき子』という日本で流布したひとつの児童文学作品の源流を探る。
渡辺貴規子[ワタナベキミコ]
著・文・その他
目次
第1部 Hector Malot,Sans famille(1878)―原典成立の背景と意義(伝記的事実とSans famille成立の背景;Sans familleと共和国;Sans familleにおける社会批判 ほか)
第2部 明治時代後期の日本におけるSans familleの翻訳受容(五来素川訳『家庭小説 未だ見ぬ親』(1903年)
菊池幽芳訳『家なき児』(1912年))
著者等紹介
渡辺貴規子[ワタナベキミコ]
1983年大阪府生まれ。2006年京都大学文学部人文学科フランス語学フランス文学専修卒業。2008年ピカルディー・ジュール・ヴェルヌ大学大学院文学研究科修士課程修了。2009年京都大学大学院人間・環境学研究科修士課程修了。2013年京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程研究指導認定退学。2016年京都大学博士(人間・環境学)取得。現在、日本学術振興会特別研究員(PD)、京都大学非常勤講師。専門、フランス児童文学、日本児童文学、日仏比較文学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-

- 和書
- 商標 (第3版)