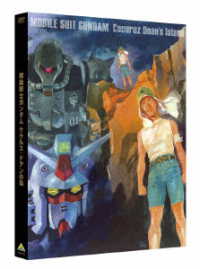出版社内容情報
カンブリア紀の爆発で出現した多種多様な生物。彼らはすばやく動く能力をそなえていた。それは外部環境を知る生物の情報処理器の変容ももたらした。この「移動能力の向上―情報処理器の洗練」が、進化に深くかかわっていたのか?
南極、ケニア、フィンランド、イタリアなど、世界各地に赴き、生き物たちに接して筆者は何を考えたのか。人間社会を含め、生物を真に理解する旅を紹介。今回の文庫化にあたり、補章を追加。
【目次】
第1章 多様な生き物たち
一 南極の虫(スプリングテールを求めて/極寒の地でも凍らない/スプリングテールも昆虫?)
二 多様な生物とその整理法(生物の分類/形変われば種も変わる?)
三 なぜ生物は多様なのか(生命の誕生/大量の酸素/原核生物から真核生物へ)
四 生物多様化の促進――多細胞生物の出現(細胞の塊/移動する能力)
五 スコット・ハット(サバイバル・トレーニング/南極の研究室)
第2章 生き物はいかに多様化したのか
一 南極の海(生命溢れる海/黄色い服を着たままバーに入るな!)
二 カンブリア紀の大爆発――多様な生物のほんとうの意味での出現(にぎやかな時代へ/体に堅いものがあるという特典/移動する方法/筋肉の存在)
三 生物の多様化の発見(生物の類縁関係――多様な生物の世界を五界説で分類した意味/ダーウィンの洞察/遺伝の法則――メンデルの工夫/生き物の形づくり/形はいかに変化するか)
四 なにをもって昆虫とするか――スプリングテールを見ながら考えた(体節で考える/翅と卵で考える)
第3章 生物がもつ時計――多様な生物の共通性
一 体内時計(別のトビムシ/白夜はツラい/二四時間一周期――概日リズム/シアノバクテリアのもつ時計)
二 氷の上で……(トビムシ捕獲作戦/ジョークとレジ袋)
三 体内時計の調べ方(光を受けとる細胞/トビムシの餌/一二時間周期/南極のタコ料理)
第4章 多細胞生物の設計原理
一 息が苦しい(ケニアの石っころ/オーストリアン・ハット/肺の役割/ヒトの呼吸調整能力)
二 生命を維持する工夫(細胞の役割分担/ホメオスタシス/生体エネルギーの通貨/太陽のめぐみ/ミトコンドリアの仕事/バクテリアの生き残り戦略?)
三 進化スピードの上昇――移動性がもたらしたもの(神経系の誕生/神経系の集中/標高五〇〇〇メートルを飛ぶハチ)
第5章 生き物たちの存在様式
一 栄養をいかに取り入れるか(家畜化されたヒト――ナイロビナショナルパークにて/エネルギー(栄養)という視点から見た生物)
二 太陽の恩恵(食物連鎖/エネルギー(栄養)の流れ/もとをたどれば太陽エネルギー/万物流転)
三 集団――群れることの効用(マガディ湖でみつけた温泉/テラピアの味/生態学とはなにか/還元論的生命観/個体の集団/個体群の広がり)
四 分布――他者との距離(個体の分布/個体数を変動させる外的要因/バッタの大発生――密度効果が集団におよぼす影響/マサイマラナショナルパーク)
第6章 生き物たちの情報戦略
一 食う食われる(フィンランドの湖畔にて/被食者と捕食者の関係/行動がもたらしたもの)
二 外部環境を知る能力(生き物たちのセンサー/運動性能を向上させた感覚器官/複雑な眼の進化/よく似た基本設計)
三 生物の情報戦略――行動と情報処理(動物の行動とは/行動の五つの単位/あらためて動物の行動とは)
四 進化
目次
第1章 多様な生き物たち(南極の虫;多様な生物とその整理法;なぜ生物は多様なのか;生物多様化の促進―多細胞生物の出現;スコット・ハット)
第2章 生き物はいかに多様化したのか(南極の海;カンブリア紀の大爆発―多様な生物のほんとうの意味での出現;生物の多様化の発見;なにをもって昆虫とするか―スプリングテールを見ながら考えた)
第3章 生物がもつ時計―多様な生物の共通性(体内時計;氷の上で……;体内時計の調べ方)
第4章 多細胞生物の設計原理(息が苦しい;生命を維持する工夫;進化スピードの上昇―移動性がもたらしたもの)
第5章 生き物たちの存在様式(栄養をいかに取り入れるか;太陽の恩恵;集団―群れることの効用;分布―他者との距離)
第6章 生き物たちの情報戦略(食う食われる;外部環境を知る能力;生物の情報戦略―行動と情報処理;進化の原動力)
第7章 驚異のナビゲーション能力(またまた別のトビムシの研究;いかに巣に帰るか―ベニツチカメムシの戦略;複雑化した行動と情報処理)
第8章 生物がつくりあげる世界―環世界(;バッファローは馬鹿者なのか;環世界の導入;種によって違う感覚の受容範囲)
第9章 環境への適応戦略(環世界をいかに理解するか;環境の変化に上手に適応したフナムシ;環世界の理解はなにをもたらすか)
第10章 環世界と文化的行動(挨拶行動が意味すること;経験によって変化する自分;生物の誕生、情報世界、そして環世界と文化世界―「まとめ」として)
補章 自然への感性を育むために
- 評価