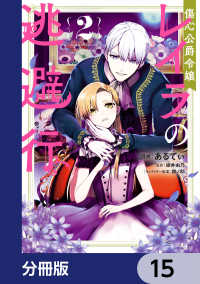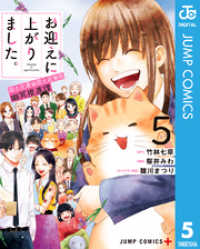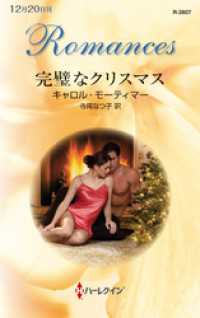内容説明
食材としてではなく、キャラクター化された姿でもなく、腕で考える動物の面目躍如たる知的能力。
目次
第1章 タコの知られざる横顔(タコの国;タコとは誰か ほか)
第2章 賢者としてのタコ(知性をつくり出すもの;学び覚えるタコ ほか)
第3章 タコの社会を考える(社会的なイカと非社会的なタコ;社会的なタコ ほか)
第4章 タコが認識する世界(視覚の動物;腕で考えるタコ ほか)
第5章 タコ学の挑戦ふたたび(サル学とのアナロジー;タコの赤ちゃん学 ほか)
著者等紹介
池田譲[イケダユズル]
1964年、大阪府生まれ。93年、北海道大学大学院水産学研究科水産増殖学専攻博士課程修了。博士(水産学)。スタンフォード大学、京都大学、理化学研究所を経て、2003年、琉球大学理学部助教授。現在、琉球大学理学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ホークス
42
2020年刊。頭足類(タコとイカ)は軟体動物に含まれ、貝類や太古に栄えたアンモナイトとは親戚。著者は多くの研究を踏まえ、無脊椎動物では脳が最大であるタコを探究する。水面から目だけ出して人を観察する憎めない生き物。高い学習能力と寿命の短さ(一年程)が不釣り合いだが、単独生活では不可欠な好奇心や観察力が学習へとつながるようだ。遊ぶ習性も、試行錯誤する能力の延長らしい。人に当てはめて考えると深い。吸盤には高感度のセンサーが沢山あり、物の凸凹から味まで感じとる。本書は業界や先輩への仁義切りがやや多いけど面白かった2025/01/25
おーすが
18
「タコとは何か」から始まり脊椎動物に比肩する大きな脳、その知性、生み出される社会、タコの認知世界へとはなしはすすむ。日本と世界のタコ研究の概略もわかりやすく面白い。イギリス人はタコが嫌いなのか…。数々の実験も紹介される。ゴムホース実験の「やったことにケリをつける」行動からはタコの時間の認知がわかるような気がするし、iPadを使った実験からわかるタコのクロスモーダル知覚には驚かされる。触覚に全フリして生きる姿に、殻を捨てた貝としてのタコのいきざまが見えるよう。2022/04/26
はやたろう
17
超流し読み。まあタコは賢いってことが分かる。ただ中身が専門的過ぎて頭に入ってこない。2024/08/29
今庄和恵@マチカドホケン室コネクトロン
14
コロナが終息して居酒屋に気兼ねなく行けるようになったら私はイカとタコを注文してこの本で得た知識をこれでもかと披露することだろう。いや、できない(どっちやねん)。タコ、食べれないよ。イルカやクジラを過激に保護するクラスタと同じだよ、こんな賢くてカワイイもの食べれないよ!ナマコを人類史上初めて食べた人は偉大だと思うのだけど、タコが絵を見分けるかどうかというテストをしようとか思いつく人がすごくね?不本意にイカ専門家と目された著者が、じゃあタコでも、と研究を始められたようで、チャーミングな文体でページをめくる手が2021/02/28
スプリント
10
タコ学も奥が深い2021/02/26