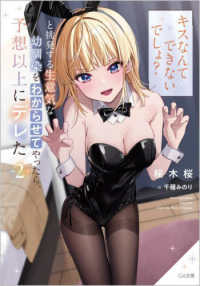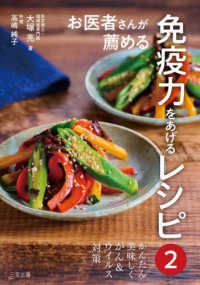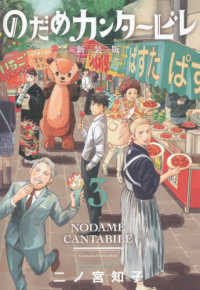内容説明
日常の何気ない行為、「見る」こと。単純で簡単なことのようだが、「ものを見る」「ものが見える」とき、脳はどんな仕事をしているのか?また、「見る」ことの解明は、心のできごとに、どうつながるのか?錯視図形、誰もがもつ盲点などの、さまざまな例を入り口に、脳研究の最前線から、脳と心の関係を考える。ワクワクするような最先端脳科学への旅。
目次
第1章 見るなんて、心のうち?
第2章 知覚と行動のつじつま
第3章 見るための脳の仕事
第4章 見る脳を覗く
第5章 心をつかさどるニューロン活動を求めて
第6章 二つの目で見る
第7章 脳、心、脳科学と私
著者等紹介
藤田一郎[フジタイチロウ]
1956年、広島県生まれ。84年、東京大学大学院理学系研究科動物学課程修了。理学博士。岡崎国立研究機構生理学研究所、カリフォルニア工科大学、理化学研究所、新技術事業団を経て、94年、大阪大学医学部教授。大阪大学大学院生命機能研究科教授、および同大学基礎工学部と行動経済学研究センター兼任。生理学、解剖学、心理学、計算モデルなどの手法をあわせて、視覚の脳内メカニズム解明をめざした研究を行っている(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
M
6
「見る」という行為に伴う脳の処理の複雑さがよくわかる本であり、ものを見ることの本質は、網膜に映る二次元的情報に基づき、脳の中で目の前の世界の三次元構造を推定し、復元され続けていることだという。推定は情報量に左右され、「見る」と「見える」では脳の処理は別の過程を経ており、その復元されたものを主観的に感じ、それに基づいて行動しているのだ。成功の秘訣などに「人ではなく環境を変える」と言われることがあるが、それは復元された内容を主観的に判断した結果、現状では成功の推定が困難であることが見えているからかもしれない。2020/02/25
takao
3
p.204 自分のまわりの世界の音、色、香りなどが、そこにあるのではなくて、半分は脳がつくったものである。 2023/11/30
金平糖
3
「脳ブームの迷信」が面白かったので、本書も読んでみました。大阪大学基礎工学部生物工学の二年生の授業の「脳科学入門」の内容をベースに執筆されたものだそうで、第五章と第六章は少々難解でしたが、第三章まではとても興味深く読みました。『自分の周りの世界の音、色、香りなどが、そこにあるのではなくて、半分は脳がつくったもの』という件が感慨深く、哲学性を感じてしまいました。2011/05/29
nitoytk
2
人が音程を感じるのは、さまざまな音の波長に対して反応するニューロンが別々に存在し、対応したニューロンが都度発火して認識する。別の本だけどそうなのかと感心した。 この本で、視覚もこれに近い認識方法らしいことがわかった。縦の線分に強く反応するニューロン。横線への反応は薄い。さまざまな角度の線分の認識は、それぞれに対応するニューロンが反応しているそうだ。 個々のニューロンの反応から、「私が三次元を視覚的に認識しているという意識」の仕組み。そんな総合的な脳の解明には、まだまだ、長い長い時間がかかるのだろう。2022/09/12
葵
2
レポートのために借りたが、普通に読み物として興味深かった。脳科学の勉強がしたくなった。文章の書き方も上手く、専門的なことを説明した後には必ず平易な言葉に置き換えてくれているため、比較的分かりやすい。最後の禅僧とのお話にほっこりした。2019/04/28