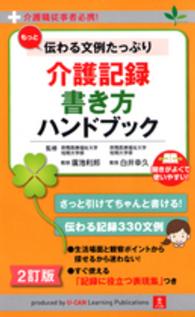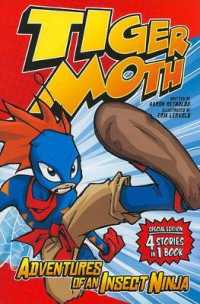- ホーム
- > 和書
- > 医学
- > 臨床医学一般
- > 画像診断・超音波診断学
内容説明
現代医療に必須のツール・MRIを理解するために。MRIで何がみえ、何ができ、何がわかり、これから何を診ようとしているのか。
目次
1章 なぜMRIで体の中がみえるのか(体の中を診る方法;MRIを知るためのABC;MRIの画像はどうしてできる)
2章 MRI装置の話(MRI装置の構成;MR信号を作りだす磁石;勾配磁場の発生;ラジオ波(RF)コイル)
3章 MRIができること(代謝情報の画像化;13C‐MR画像;代謝産物の追跡;こんなこともできるMRI)
4章 脳の活動をfMRIで診る(fMRIの特長;MR法の造影効果;fMRI導入への糸口;fMRIの応用例)
5章 MRIはこれから何を診ようとしているのか(鮮明なMR画像を得る;ES細胞の体内追跡;アルツハイマー病を診る;応用への展望;課題の克服)
著者等紹介
犬伏俊郎[イヌブシトシロウ]
1978年京都大学大学院工学研究科石油化学専攻修了。工学博士。1978年米国ペンシルベニア大学医学部生物物理化学科博士研究員。1980年NIH National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases(NIDDK)Visiting Fellow。1983年米国ペンシルベニア大学医学部NMR研究施設室長。1984年同大学医学部生物物理化学科助教授。1990年滋賀医科大学分子神経生物学研究センター客員教授。1994年滋賀医科大学分子神経生物学研究センター教授。2000年分子神経科学研究センターに改組。2003年MR医学総合研究センターセンター長教授。専門は物理化学と生物物理。現在の興味は生体内の化学反応動力学の解析と生理的情報の可視化、分子イメージング日本化学会、日本磁気共鳴医学会(会長)、日本分子イメージング学会(副会長)、日本分子生物学会、日本再生医療学会、米国化学会、米国生物物理学会、国際磁気共鳴医学会などに所属(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。