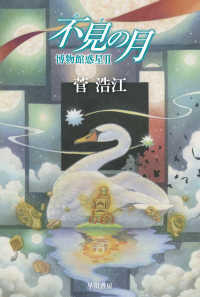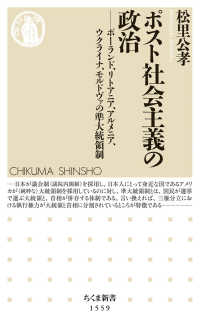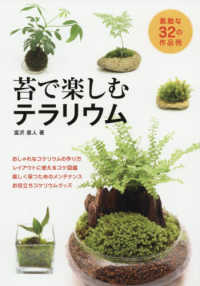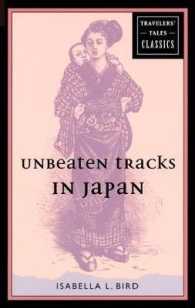- ホーム
- > 和書
- > 人文
- > 文化・民俗
- > 文化・民俗事情(日本)
内容説明
日本人は、いかなる「知恵」と「しきたり」のもとで食して、健康長寿をたもってきたか。「うまい・ヘルシー・長生き」の三拍子そろった和食の実用性、日本の「食」の素晴らしさと、それにまつわる「知恵」と「しきたり」の奥深さ。
目次
知っておきたい!1 この「食」の始まり(すし―元来のすしは「握りずし」とは似ても似つかぬものだった;カツオ、サンマ―これぞ、旬食の極み ほか)
知っておきたい!2 食事の作法とその心得(「いただきます」の意味―神聖な山の神への感謝の心の表れだった;箸の文化―いつから「二本の箸」で… ほか)
知っておきたい!3 伝統行事の「食」のしきたり(ハレの日に食べる赤飯―お祝いごとや神事に欠かせないのは、なぜ?;小豆がゆ―小正月を祝って食べ、破邪と健康を得る ほか)
知っておきたい!4 人生の節目の「食」のしきたり(お食い初め―お乳以外の食べ物を口にする人生最初の儀式;一升餅―山あり谷ありの「一生」に、親族一同の思いを込める ほか)
知っておきたい!知っておきたい!5 調理道具と調理・調味の数々(調理の原点は「石焼き」―「包み焼き」「蒸し焼き」へと発展;「焼き」から「煎る」へ―そして「揚げ」の調理法が登場 ほか)
著者等紹介
永山久夫[ナガヤマヒサオ]
1932(昭和7)年、福島県生まれ。食文化史研究家。元西武文理大学客員教授。食文化研究所所長。綜合長寿食研究所所長。永年、日本の伝統的な食文化の研究を続け、和食による健康・長寿を提言。時代劇ドラマでは食膳の考証を行うなど、多方面に活躍している食文化史研究の第一人者(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
壱萬参仟縁
高橋直也