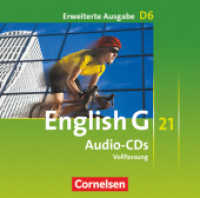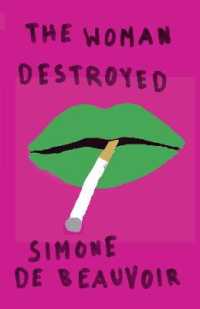目次
どもりって何ですか?
どもりは差別語ではないのですか?
どんな時に吃るのですか?
どもりの原因って何ですか?
これまでどのような「治療」がなされてきましたか?
吃る人の悩みとはどのようなものですか?
アメリカの専門家は吃音の問題をどうとらえていますか?
どもりは障害ですか?
なぜ、「どもりを治す」ではなく、「つき合う」なのですか?
子どものどもりは、放っておいたらほとんどが治るので心配ありませんと言われましたが、本当ですか?〔ほか〕
著者等紹介
伊藤伸二[イトウシンジ]
1944年、奈良県生まれ。明治大学文学部・政治経済学部卒業。大阪教育大学特殊教育特別専攻科修了。大阪教育大学専任講師(言語障害児教育)を経て、現在伊藤伸二ことばの相談室主宰。日本吃音臨床研究会会長。大阪教育大学非常勤講師。言語聴覚士養成の専門学校3校で吃音の講義を担当。小学2年生の秋から吃音に強い劣等感をもち、1965年に吃る人のセルフヘルプグループ、言友会を設立するまで吃音に深く悩む。現在は大阪スタタリングプロジェクトでセルフヘルプグループの活動を続けている。1986年に第1回吃音問題研究国際大学を大会会長として開催し、世界35か国が参加する国際吃音者連盟の設立にかかわる。現在国際吃音者連盟の顧問理事。セルフヘルプグループ、論理療法、交流分析、アサーティブ・トレーニング、竹内敏晴「からだとことばのレッスン」などを活用し、吃音と上手につき合うことを探る。吃音ワークショップ、吃音親子サマーキャンプ、臨床家のための吃音講習会などを開催している
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。