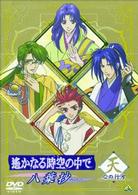内容説明
多様な姿を見せる日本語・琉球諸語の諸変種。それらが分かれる以前の祖語の姿はどのようなものだったのだろうか。そこからどのような歴史変化が起こって、現在見るような動詞の活用や指示詞の体系は出来上がったのだろうか。また、諸変種はどのような順番で分岐し、その上でどの程度の接触・混交が起こったのだろうか。日琉諸語の分岐発展・歴史変化に、言語学的・統計学的手法で迫る意欲的な論文集。
目次
第1部 系統を考える(日琉諸語の系統分類と分岐について;分岐学的手法に基づいた日琉諸語の系統分類の試み;「日本祖語について」と『日本祖語の再建』―その継承と発展のために)
第2部 系統研究の可能性(DNAと言語をつなぐ;琉球諸語研究における方言系統地理学の可能性;方言群の時空間動態の統計的モデル化に向けての予備的考察)
第3部 諸方言から歴史変化へ(琉球諸語と上代日本語からみた祖語の指示体系試論;方言研究から歴史変化を、歴史変化から方言解明へ;不規則性の衰退―日本語方言の動詞形態法で起きていること;八丈語の古層)
著者等紹介
林由華[ハヤシユカ]
国立民族学博物館・外来研究員。専門は言語学・日本語学、特に宮古語を中心とした琉球諸語における文法記述および言語記録
衣畑智秀[キヌハタトモヒデ]
福岡大学人文学部・教授。専門は日本語学。特に文法の歴史変化と琉球宮古語の研究
木部暢子[キベノブコ]
国立国語研究所・特任教授。専門は日本語学。特に西南部九州における二型アクセントの研究、文末イントネーションの類型論的研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
いとう・しんご
中村明裕