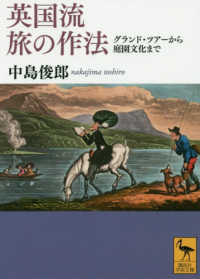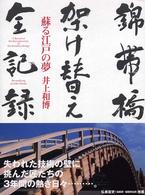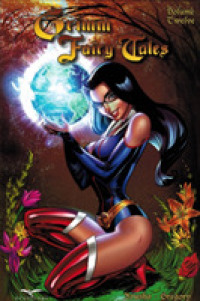内容説明
言語表現はヒトに固有の生得的能力と生後の社会文化的経験に由来する。言語の普遍性や多様性もこの両面とかかわる。誰でも5・6歳で母語を自由にあやつるが、世界をどのように意味づけるかは、社会的な価値観などとも関連し、語・文からだけでは説明できない。言語活動の全域に迫るためには、分析対象を談話にまで拡大し、意味上「言説の秩序」を導入して多様な因子を統合する必要がある。そうしてはじめてあいまいさを好む日本語「人」の特徴なども明らかになる。
目次
第1章 20世紀の言語学―分析対象の縮小とその結果
第2章 ヒトと言語と社会
第3章 人の性向と言語表現
第4章 言語分析の再編に向けて
第5章 意味分析の対象拡大により見えてくるもの―言語分析から人文社会科学へ
第6章 日本の言説の秩序―あいまいさがなぜ許されるのか
第7章 価値観の重層性
第8章 ことばが力を失うとき
第9章 大学における外国語教育
著者等紹介
児玉徳美[コダマトクミ]
1935年、広島県生まれ。1958年、神戸市外国語大学英米学科卒業。1975年、ロンドン大学留学。立命館大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。