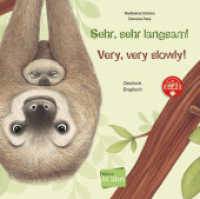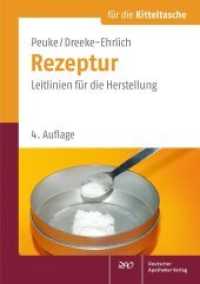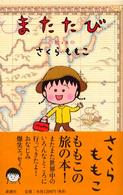内容説明
半世紀余にわたる著者の英文法研究を集大成し、渾身の力をふりしぼって書きあげたライフワーク。豊富な用例を著者の文法観に基づいて体系化した学術書であると同時に、常に座右に置いて、英文法上の疑問が浮かぶごとに参照できるreference grammarである。その際、英語の文法現象のhowを記述するにとどまらず、常にwhyという疑問に答えようとした。
目次
文型
文の要素
時制と相
現在時制
過去時制
未来時を表す表現形式
進行形
完了形
完了進行形
Be、Have、Do〔ほか〕
著者等紹介
安藤貞雄[アンドウサダオ]
1944年関西大学専門部中退。1949年文部省英語教員検定試験合格。1973年ロンドン大学留学。1976年市河賞受賞。島根大学、広島大学、関西外国語大学、安田女子大学の教授を歴任、現在、広島大学名誉教授・文学博士(名古屋大学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。