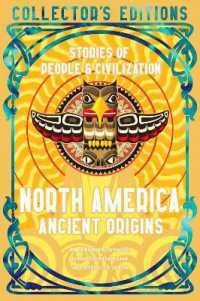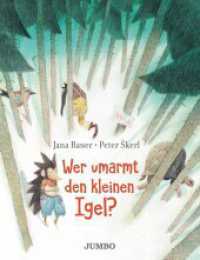内容説明
いつの時代も生きて行くのは切ねェものよ―「福助」の息子の良助が、早朝、両親の弘蔵とおあきに、最後の挨拶にやって来た。良助は武士にあこがれ、彰義隊の一員になっていたが、上野の山の戦に参加するためだった。そして、いよいよ本所にも大砲の音が聞こえてくる。おあきたちは、懸命に無事を祈るのだが…。幕末・江戸の見世を舞台に、健気に生きる人びとの、人情と人生の機微を描き切った、著者献身の傑作時代長篇。
著者等紹介
宇江佐真理[ウエザマリ]
1949年、北海道函館市生まれ。95年「幻の声」で第75回オール讀物新人賞受賞。2000年『深川恋物語』で第21回吉川英治文学新人賞受賞、01年『余寒の雪』で第7回中山義秀文学賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ふじさん
98
庶民の目線で語られる疾風怒涛の幕末物語は、面白く、分かりやすく、新しい発見もあり、歴史の案内書になっている。時代の流れは、ささやかな幸せを望む市井の人々も巻き込む、福屋の一家も例外ではない、孫が生まれる幸せもつかの間、跡取り息子の良助が父親の故郷の松前で死ぬ。子を持つ親の喜びと悲しみは尽きない。生きる喜びと切なさと哀しみ、幕末の江戸の見世を舞台に、時代に翻弄されながらも、健気に生きる人々の息づかいが伝わる著者献身の傑作時代長編。巻末の児玉清の解説は、素晴らしいの一言。何度読んでも心に染み入る。2024/02/24
chimako
95
一気読みだった。彰義隊に入った息子の良介。おていのお産。「福助」の二人には気の休まるときがない。一番の心配事だった戦が上野のお山で始まってしまった。良介を案ずる二人。命からがら逃げ帰った良介を弘蔵は松前藩の知り合いに頭を下げかくまってもらうが………子を亡くす事ほど辛く悲しい事はない。周りを取り巻く人たちの心遣いがまた泣かせる。『夕映え』この言葉があらわれる場面はまるで二人と共に空を見上げているような気がした。しみじみと良い本でした。解説は児玉清さん。思わぬ贈り物をされたように嬉しかった。2016/05/03
ぶんこ
65
幕末から明治への激動の時代、本所深川の一膳飯屋一家も波にのまれ、長男良助は命をました。 それでも市井の人々の暮らしは続き、明治となった激しく変動する時代を黙々と働いて生活しています。 歴史や小説の中で知っていた江戸から明治への変遷が、より身近に感じられました。 戦の最前線にたつ兵士の多くが、人減らし、食べる為だという事にも考えさせられました。 長崎のグラバー邸は有名ですが、死の商人だったとは知りませんでした。2015/12/23
優希
45
時代の動乱に巻き込まれていく市井の人たち。それでも強く生きようとする人々が健気でした。人情と人生の機微が鮮やかに描かれていたと思います。2021/12/30
ゴルフ72
39
時代としたらこの幕末から明治が一番面白いがそこで生きた人たちにとってはまさに急転直下で時間が動いたかもしれない。弘蔵とおあきの息子良助の死はとてつもなく悲しいものだった。そんな中、新しい命も生まれる・・・明治という時代は彼らに何を見せるのだろう2021/11/15
-
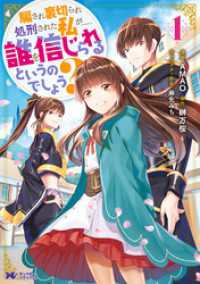
- 電子書籍
- 騙され裏切られ処刑された私が……誰を信…