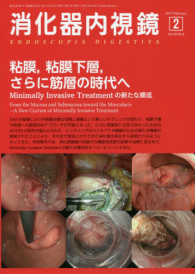内容説明
幕末・江戸の本所に、「福助」というおでんが評判の縄暖簾の見世があった。女将のおあきは、父親の跡を継いで、十六になる娘のおていとともに、見世を切り守りしていた。亭主の弘蔵は、松前藩の元武士で、町の人々から頼りにされている岡っぴき。夫婦の心配の種は、職を転々として落ち着かない長男の良助のこと。江戸から明治に代わる時代の大きな潮流に、つつましく幸せな暮しをしていた、おあきたち市井の人々も、いやおうなく巻き込まれていく…。
著者等紹介
宇江佐真理[ウエザマリ]
1949年、北海道函館市生まれ。95年「幻の声」で第75回オール讀物新人賞受賞。2000年『深川恋物語』で第21回吉川英治文学新人賞受賞、01年『余寒の雪』で第7回中山義秀文学賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
chimako
96
長々持ち歩いて2/3程読んだところだったが、この連休で最所から読み直し。宇江佐さんの世界にどっぷりと浸かることが出来た。時は幕末。不安定な世の中だが、変わらぬおでんと旨い惣菜の一膳飯屋「福助」。切り盛りするのはおあき。亭主は岡っ引きの弘蔵。訳ある二人が一緒になりささやかな幸せを築いていた。心配なのは息子の良介と娘のおてい。何時の時代も親の想いは変わらぬもの。職を転々としていた良介がやっと見つけたのは彰義隊。命をかける仕事だった。娘の嫁入りのごたごたやら日々の暮らしやら。時代は今、動こうとしている。2016/05/03
ふじさん
95
幕末の江戸の本所にあるおでんが評判の縄暖簾「福助」の舞台にした市井小説。父親の跡を継いだ女将のおあき、元は松前藩の武士で今は岡っ引きの弘蔵、見世の切り盛り手伝う16歳になる娘のおてい、職を転々として落ち着かず夫婦の心配の種の長男の良助。江戸から明治に波瀾万丈の時代の流れに翻弄されながらも幸せな暮らしをしていた家族も、否応なく時代の流れに巻き込まれる。市井の視点で、幕末の混乱を語る作品、どんな結末を迎えるのか、楽しみ。 2024/02/23
ぶんこ
66
宇江佐さんには珍しい幕末物でした。 彰義隊に入って行く長男良助。 その時「食べる事、寝る場所に困らない」の話があり、ふとアメリカなどで志願していく兵士には毎日の衣食住に困っている若者が多いという話を思い出しました。 なんだか切ないです。 江戸の町で狼藉し放題の官軍を、なぜ放置したのか官軍トップの見識を聞いてみたい。 本所の片隅で「福助」を開き、地道に暮らすおあきと弘蔵、青物問屋に嫁にいったおてい。 市井の人々の生活が、どのようになっていくのか下巻を続けて読みます。2015/12/23
kei302
46
江戸幕府崩壊。おあきたち市井の人々もいやおうなしに巻きこまれていく。彰義隊、薩摩の台頭。江戸消滅の危機。史実を互いの立場で分かりやすく説明してあるので、読みやすい。八百半の青梅の身に起きたことには言葉を失う。そして、おていと半次郎がどうなるのか気をもんだ。どうする、良介。下巻に続く。 2020/05/17
優希
45
幕末動乱の時代の中、「福助」というおでん屋を営む夫婦と親子。明治へと変わる時代の潮流につつましい幸せが壊れないかと不安になりました。下巻も読みます。2021/12/30
-

- 電子書籍
- コンメンタール民事訴訟法IV(第2版)