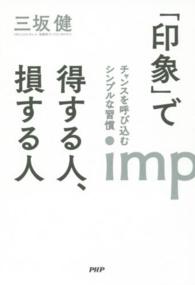内容説明
日本語では、主語がしばしば言語化されずに発話がなされる。いわば、非言語状態で概念化がなされないままの主語と、発話された述語との組み合わせでコミュニケーションが行われるのである。西洋の言語ではなく、そうした日本語の本質にそって、言語行為や文法についての考察を行った。さらに小説、映画、演劇、落語などに至る広いジャンルに及んで調査分析をして、日本語教育、国語教育のために具体的、実践的に考察を行った。
目次
第1部 現代語の品詞分類法―「日本語」と「国語」の教育のために(自立語;補助語;付着語)
第2部 語法と語史(日本語の会話文における題目部の外在(ないし内在)について
学校文法と接尾用言―「書きヤスイ」と「美しスギル」をめぐって
古代における「もの」と「こと」
準体助詞・準体法・ク語尾
「~ハズダ」 とその周辺、およびその成立
古代文学に見る失意・後悔の表現
「~ヨウニナル」 の語法、およびその成立)
第3部 国語教育と方言(国語教育のための考える文法―「ある」「ない」をめぐって;国語と差別―方言および敬語をめぐって;ことばの実験教室―方言の語法、家族の呼び方、ニュー・フォークの文体;神戸の文学と関西方言―谷崎潤一郎、野坂昭如、田辺聖子、宮本輝、坂本遼、その他;神戸市におけるテヤ敬語の衰退―大学生の方言使用に関して)
(増補)(日本語の「主語」と小説の文体―谷崎潤一郎『痴人の愛』『文章読本』志賀直哉『暗夜行路』をめぐって;宮本輝と関西方言;田辺聖子作品における関西方言について;関西のことばと文化―小説・詩・落語・マンガ・映画;西鶴・近松作品と上方詞―国語教育の観点からみる関西方言資料としての文学作品;神戸市における方言敬語の衰退について―大学生とハル敬語、テヤ敬語の状況)
著者等紹介
小谷博泰[コタニヒロヤス]
昭和19年1月神戸市に生まれる。昭和49年3月甲南大学大学院人文科学研究科国文学専攻博士課程単位取得満期退学。甲南大学文学部助手、講師、奈良教育大学教育学部講師、助教授を経て、甲南大学文学部教授、甲南大学大学院人文科学研究科国文学(日本語日本文学)専攻教授。平成24年3月定年退職。甲南大学名誉教授。古事記学会理事、木簡学会評議員、全国大学国語国文学会委員を務めた(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。