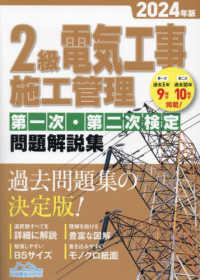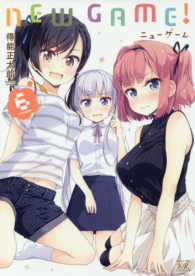出版社内容情報
古事記、万葉集の成立や筆録の過程について、飛鳥藤原時代木簡などの新出資料の研究を基に、特に文章表記、用字を軸に考察。1988年に上代の新しい資料として、長屋王家木簡・二条大路木簡など多量の重要な文字資料の出現があった。その後も、飛鳥池遺跡・屋代遺跡・観音寺遺跡等から驚くべき木簡資料が次々と報告された。この時期に当って、木簡の研究をもとに、上代の文学作品についても新たな考察を行なった。
口絵 木簡資料写真/第一部 文章史から見た古事記の成立 1古事記の表記と表現 2文の接続にかかわる語をめぐって 3記紀の神名と寿詞の表記 4上代の表記法と古事記 5古事記の成立と日本書紀 6海幸山幸説話に関する記紀の比較 第二部 万葉集の表記と用字 1万葉集と文字 2巻一・巻二の用字と表記 3柿本人麻呂作歌の同語異表記について 4巻十九における大伴家持の表記法 第三部 木簡・文書の表記と語彙 1上代の金石文・木簡・文書 2宣命・祝詞の表記と語彙 3古事記と木簡 4風土記と木簡 5木簡に見る和風表記と上代文書 6飛鳥藤原時代木簡の表記法をめぐって (増補)木簡・文書の文字使用に関する一考察―基本的課題をめぐって―/著者名索引・事項索引
小谷博泰[コタニヒロヤス]
著・文・その他
内容説明
古事記、万葉集の成立や筆録の過程について、上代の国語史を塗り替えるような飛鳥藤原時代木簡などの新出資料の研究を基に、特に文章表記、用字を軸に考察した。従来は等閑にされていた宣命体文章について、和漢混淆文、漢字仮名交じり文の先駆をなすものと考察した著作集第一巻を視野に置き、その研究成果を応用し、発展させたものである。さらに広く、祝詞や風土記などについての考察をも併せて行う。
目次
第1部 文章史から見た古事記の成立(古事記の表記と表現;文の接続にかかわる語をめぐって;記紀の神名と寿詞の表記 ほか)
第2部 万葉集の表記と用字(万葉集と文字;巻一・巻二の用字と表記;柿本人麻呂作歌の同語異表記について ほか)
第3部 木簡・文書の表記と語彙(上代の金石文・木簡・文書;宣命・祝詞の表記と語彙;古事記と木簡 ほか)
増補 木簡・文書の文字使用に関する一考察―基本的課題をめぐって
-

- 和書
- 大好き、フランス語!