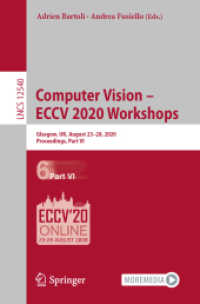出版社内容情報
約17000首の和歌を収めた小沢蘆庵の自筆家集『六帖詠藻』を初めて翻印公刊。論考3本、人名・和歌連歌/漢詩初句索引付き。蘆庵の神髄、いよいよ
その和歌、およそ17000首。歌論家として知られる小沢蘆庵(1723‐1801)の、和歌の全貌を初めて翻印公刊。歌論的言説も、連作の妙味も、妙法院宮真仁法親王や上田秋成との雅交も、あるいは双六歌や沓冠歌などの〈遊び〉も、蘆庵の日々の和歌の営みが、すべてここに明らかに――。
蘆庵自筆の静嘉堂文庫蔵本(50巻47冊)を底本とし、他本と校訂をして翻字。加藤弓枝「自筆本『六帖詠藻』と板本『六帖詠草』」ほか3本の論考を併載し、「人名索引」「和歌連歌/漢詩初句索引」を添える。収載された700名を超える人名はまさに蘆庵の交遊圏そのもの。蘆庵の和歌的生活がつぶさに知られて貴重である。
こたびの公刊は、かつてこの難事に挑み、蘆庵文庫本(現京都女子大学図書館蔵)を底本として全巻の翻字と他本との校合を終えながらも公刊を果たし得なかった医者にして蘆庵研究の先達、中野稽雪・義雄父子の意思を引き継いだ、いわば60年越しの宿願の成就にほかならない。
緒言―近世和歌史と小沢蘆庵― 神作研一
第一部 本文編 編集・校訂 飯倉洋一・大谷俊太・加藤弓枝・神作研一・盛田帝子・山本和明
翻字凡例
六帖詠藻
春一?春十一
夏一?夏六
秋一?秋十
冬一?冬六
恋一?恋三
雑一?雑十三
第二部 研究編 加藤弓枝
はじめに
論文1 自筆本『六帖詠藻』と板本『六帖詠草』
論文2 小沢蘆庵の門人指導―『六帖詠藻』に現れる非蔵人たち―
論文3 『六帖詠藻』と蘆庵門弟―自筆本系の諸本を通して―
第三部 索引編 大谷俊太・加藤弓枝編
索引凡例
人名索引
和歌連歌初句索引
漢詩初句索引
後書 大谷俊太
蘆庵文庫研究会[ロアンブンコケンキュウカイ]
飯倉洋一
1956年生まれ。大阪大学大学院文学研究科教授。博士(文学)。著書『秋成考』(翰林書房、2005)、『上田秋成―絆としての文芸』(大阪大学出版会、2012)
大谷俊太
1956年生まれ。京都女子大学文学部教授。博士(文学)。著書『和歌史の近世 道理と余情』(ぺりかん社、2007)。
加藤弓枝
1974年生まれ。豊田工業高等専門学校一般学科准教授。博士(文学)。共著『和歌文学大系70 六帖詠草/六帖詠草拾遺』(明治書院、2013)。
神作研一
1965生まれ。国文学研究資料館教授。総合研究大学院大学教授(併任)。博士(文学)。著書『近世和歌史の研究』(角川学芸出版、2013)。
盛田帝子
1968年生まれ。大手前大学総合文化学部准教授。博士(文学)。 著書『近世雅文壇の研究』(汲古書院、2013)。
山本和明
1962年生まれ。国文学研究資料館特任教授。論文「梅を紡ぐ―京伝『梅花氷裂』私案―」(文学 第17巻4号、2016)。
内容説明
その和歌、およそ17,000首。歌論家として知られる小沢蘆庵(1723‐1801)の、和歌の全貌を初めて翻印公刊。歌論的言説も、連作の妙味も、妙法院宮真仁法親王や上田秋成との雅交も、あるいは双六歌や沓冠歌などの“遊び”も、蘆庵の日々の和歌の営みが、すべてここに明らかに―。
目次
第1部 本文編
第2部 研究編(自筆本『六帖詠藻』と板本『六帖詠草』;小沢蘆庵の門人指導―『六帖詠藻』に現れる非蔵人たち;『六帖詠藻』と蘆庵門弟―自筆本系の諸本を通して)
第3部 索引編