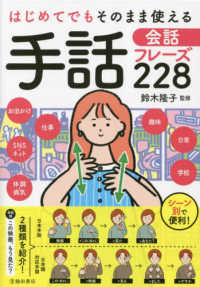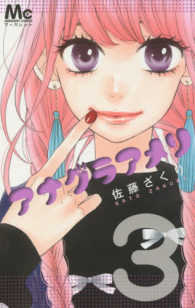内容説明
西はシルクロードを経由して「遠くイラン、インドの流を汲み、東は日本、朝鮮等に統を伝え、アジアにまたがる国際的音楽文化の中軸」(「楽制篇・自序」より)となった中国唐代音楽の、前人未踏の研究、先駆的・世界的な一大業績であり、今なお唯一の研究の基盤となり得るものである。また同時に、日本音楽史研究への影響も計り知れない。
目次
楽理篇(唐の俗楽二十八調の成立年代について;西域七調とその起源)
楽書篇(燕楽名義考;唐代音楽文献概説;唐代音楽書の輯失および解題;『楽学軌範』の開版について;最古のインド音楽書 Bharata‐Natyasastra)
楽器篇(唐代楽器の国際性;琵琶の淵源―ことに正倉院五絃琵琶について;周文矩の唐代宮妓合楽図について;前蜀始祖王建棺座石彫の二十四楽妓について;笙の不明なる四管とその日本渡伝について;唐代驃国の楽器―ミャンマー音楽の今昔)
楽人篇(西域楽東流における胡楽人来朝の意義;曹妙達)
著者等紹介
岸辺成雄[キシベシゲオ]
1912年東京に生れる。1936年東京帝国大学文学部東洋史学科卒業。1961年東京大学教養学部教授。『唐代音楽の歴史的研究楽制篇上巻』により日本学士院賞受賞。「唐代音楽の歴史的研究」により東京大学より文学博士の学位を受ける。1973年帝京大学教授。東京大学名誉教授。2005年1月4日逝く
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。