出版社内容情報
山本想太郎[ヤマモトソウタロウ]
著・文・その他
倉方俊輔[クラカタシュンスケ]
著・文・その他
内容説明
なぜ建築を競わせるのか?みんなを束ね、社会を高める建築コンペの価値を問いなおす。
目次
序 誰がためにコンペはあるのか
第1章 傷だらけのコンペ―新国立競技場コンペをめぐって
第2章 コンペの歴史が語ること
第3章 日本のコンペの仕組みはどうなっているのか―設計発注方式の変遷
第4章 「いい建築」を合意するプロセスへ―ポスト新国立競技場の建築コンペ像
終章 コンペがつくる「いい建築」
著者等紹介
山本想太郎[ヤマモトソウタロウ]
1966年東京生まれ。建築家、山本想太郎設計アトリエ主宰。早稲田大学理工学研究科修了後、坂倉建築研究所に勤務。2004年より現職。東洋大学、工学院大学、芝浦工業大学非常勤講師
倉方俊輔[クラカタシュンスケ]
1971年東京生まれ。建築史家、大阪市立大学准教授。早稲田大学理工学研究科修了後、博士(工学)。建築史の研究や批評に加え、建築公開イベント「イケフェス大阪」の実行委員を務めるなど、建築の価値を社会に広く伝える活動を行なっている。著書多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
cocomero
1
新国立競技場設計競技でコンペとは名ばかりの杜撰な手続きを目の当たりにしたことから、もはや成熟した社会にこそ必要なコンペについて、従来の在り方と実質上は消滅の要因を分析しながら、論じられる。専門家とそのアイデアを批判しえる総合性としての社会、いわばみんなが、コンペをめぐって、完成に至るまで議論し続け、その都度の状況に応じて修正補完しつつ、「いい建築」の実現を目指す。専門家同士の一時的なアイデア決定という閉鎖的な慣例を脱し、プロセスまでをも含めた、みんなに開かれた文化的営みとしてコンペを捉えて行うことが大切。2024/10/08
tori
1
最近隈研吾展に行き、建築家が関わるコンペというものが一体何なのか気になっていたのだが、本書がコンペの歴史や現代日本のコンペの現状を豊富な具体例とともに説明してくれたおかげで、大まかに理解できたような気がする。匿名でアイデア競争を行うコンペは、予想もしないような素晴らしい建築を生み出したり、無名の優れた建築家を発掘したりするのに大きく貢献してきたという。しかしこの方策は余裕があるからこそできるもので、建築が飽和し経済成長も鈍化した現代日本では、むしろ保守的で安価な建築に流れざるを得ない、と思うと悲しい。2021/09/21
christinayan01
0
なんでわざわざ1冊の本にしたんだろうって内容。チラ裏。「みんな」ってどこにかかってる? 新国立競技場のやり方を端にして今のコンペルール(特にやり直しで施工者コンペにすり替えられてる点とか?)をどうにか声をあげたかったのかなと思ったがこの国は土建国家なので施工業者が中心であるし、法でガチガチに守られているから言ってもどうにもならんと思う。(だから有能な設計者はみんな海外行くんだろうなと思っている。)。内容的には歴史や海外のコンペや過去の事例に半分くらい費やして、最後に既定路線のように各自の提言をして終わり。2021/04/18
-

- DVD
- サスカッチ・サンセット【DVD】
-
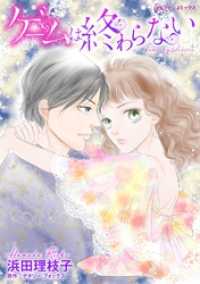
- 電子書籍
- ゲームは終わらない【分冊】 8巻 ハー…







